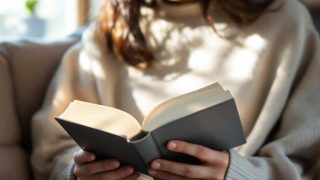自分らしい最期をどう迎える?──“葬儀”の備えと選択肢
「葬儀をどうするか」──それは“人生の締めくくり”です

終活の中でも、多くの方が最後まで手をつけにくいテーマが「葬儀」です。でも、自分らしい人生を送ってきたのなら、その締めくくりもまた「自分らしく」ありたいですよね。葬儀は遺された人のためのものでもありますが、自分の想いを反映させることは、家族にとっても大きな助けになります。
葬儀は大切な節目ですが、その選択肢は多様化しています。家族葬、一般葬など形式ごとの費用比較や、葬儀社選びのポイント、そして事前の準備がいかに家族を助けるかを具体的に解説。後悔しないお見送りのために、今できることから考えてみませんか?
増え続ける葬儀の選択肢と現状
近年、葬儀の形式は多様化が進んでいます。かつて主流だった一般葬に加え、より小規模な葬儀や、宗教色を排した形式が注目を集めています。
主な葬儀形式の例
- 家族葬: 家族や親しい友人など、ごく限られた人のみで執り行う小規模な葬儀です。近年最も選ばれることの多い形式となっています。
- 一般葬: 親族や親しい友人だけでなく、故人の会社関係者や近所の方など、幅広い弔問客を招いて執り行う一般的な葬儀形式です。通夜、告別式、火葬といった一連の儀式を丁寧に行います。新たに定着した家族葬に対して、従来からの葬儀という意味合いで一般葬と呼ばれます。以前は一般葬という言葉はありませんでした。
- 一日葬: 通夜を省略し、告別式と火葬を1日で済ませる形式です。時間的・経済的負担を軽減できます。
- 直葬(火葬式): 通夜や告別式といった儀式を行わず、火葬のみを執り行う形式です。費用を抑えたい場合や、身寄りのない方に選ばれることがあります。
- 社葬(合同葬含む): 会社が主体となって執り行う葬儀で、故人が会社に大きな功績を残した役員や従業員である場合が多いです。会社の業務として行われるため、規模が大きく、会社の格式や対外的な関係を考慮した進行が特徴です。故人の遺族と会社が共同で執り行う場合は「合同葬」と呼ばれることもあります。
- オンライン葬儀: 遠方の親族がリモートで参列できる形式です。近年、新型コロナウイルス感染症の影響もあり普及が進みました。
統計データに見る葬儀の変化とコロナ禍の影響
一般社団法人日本消費者協会の2022年の調査では、葬儀にかかる費用の全国平均は約110万円でした。これは2017年の約196万円と比較して大幅に減少しており、小規模な葬儀形式が普及していることが背景にあります。
特に、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、家族葬の普及はさらに加速しました。 感染対策として参列者の制限が求められたことや、会食を伴う形式を避ける傾向が強まったことが、少人数で執り行える家族葬の選択に繋がったと考えられます。
株式会社鎌倉新書の「お葬式に関する全国調査2024」によると、葬儀形式の選択肢では家族葬が約6割を占め、次いで一般葬、一日葬と続きます。今後もこの傾向は続くと見られ、個人の価値観やライフスタイルに合わせた葬儀の多様化はさらに進むと予想されます。
家族葬と一般葬、費用を比較してみると?
葬儀の形式を選ぶ上で、費用は重要な判断基準の一つです。
株式会社鎌倉新書の「お葬式に関する全国調査2024」によると、葬儀形式ごとの平均費用は以下のようになっています(主要項目のみ抜粋)。
- 一般葬の平均費用:約169.5万円
- 家族葬の平均費用:約110.8万円
このデータからもわかるように、家族葬は一般葬に比べて費用を抑えられる傾向にあります。家族や親しい人のみで行うため、参列者への返礼品や飲食費などが削減されることが主な要因です。
葬儀に備える「保険」という選択肢
「葬儀費用はどれくらいかかるのか」「もしもの時、家族に負担をかけたくない」といった不安を解消するために、事前に葬儀費用を準備する方法として「保険」の活用も有効な選択肢となります。
主なものとしては、以下の2つが挙げられます。
-
少額短期保険(死亡保険)
- 特徴: 保険金額が少額(一般的に1000万円以下、死亡保険の場合は100万円以下が主流)で、保険期間も短期(1年など)ですが、高齢でも加入しやすい点がメリットです。告知項目が比較的少ないため、持病がある方でも加入できる可能性があります。保険料も手頃なものが多いです。
- 葬儀費用への活用: 契約者が亡くなった際に、指定した受取人(多くは配偶者や子)に保険金が支払われます。この保険金を葬儀費用に充てることで、遺族の経済的負担を軽減できます。
- 注意点: 保険期間が短いため、定期的に更新が必要になります。また、保険会社によっては、加入できる年齢に上限があったり、健康状態に関する告知義務があったりします。
-
終身保険(死亡保険)
- 特徴: 一度加入すれば、保険料の支払期間が終了した後も保障が一生涯続く死亡保険です。保険金額も少額短期保険より高額な設定が可能です。
- 葬儀費用への活用: 契約者が亡くなった際に、受取人に保険金が支払われます。この保険金を葬儀費用だけでなく、遺された家族の生活費など、様々な用途に充てることができます。
- 注意点: 保険料は少額短期保険に比べて高くなる傾向があり、特に高齢になってからの加入は保険料が高額になることがあります。また、健康状態に関する告知が厳しく、持病がある場合は加入が難しいケースもあります。
保険を検討する際のポイント
- 加入目的を明確にする: 葬儀費用のみを賄いたいのか、それとも遺族の生活費もカバーしたいのかなど、目的を明確にすることで、適切な保険種類や保険金額が見えてきます。
- 複数の保険会社を比較検討する: 保険会社によって、保険料、保障内容、告知条件などが異なります。複数社の資料を取り寄せたり、保険の専門家に相談したりして、ご自身の状況に合った保険を選びましょう。
- 払込期間と保険料を考慮する: 終身保険の場合、保険料の払込期間を終身にするか、一定期間で払い込みを終えるかによって、月々の保険料が変わります。無理なく支払える範囲で検討することが大切です。
- 解約返戻金: 終身保険には解約返戻金がある場合が多いですが、契約後すぐに解約すると元本割れすることもあります。
保険は、万が一の際に経済的な安心をもたらす有効な手段です。ご自身の健康状態や経済状況、そして家族への想いを踏まえ、葬儀費用を含めた将来の備えとして検討してみてはいかがでしょうか。
家族葬の意外な落とし穴
費用が抑えられる、気を遣わずに済む…と人気の家族葬ですが、実は意外な落とし穴もあります。
- 知らせなかったことで後からトラブルに: 「なぜ教えてくれなかったのか」「お別れができなかった」と、故人との関係性によっては親族や知人から不満が出ることも少なくありません。
- 葬儀後の弔問対応が大変になる: 葬儀に参列できなかった人が後日弔問に訪れることになり、かえって遺族の負担が増える場合があります。特に故人と関わりの深かった方が多い場合、個別の弔問対応に追われる可能性も考慮が必要です。
- 弔いの機会を奪ってしまう可能性も: 故人にお世話になった方にとって「お別れの場」は非常に重要な意味を持ちます。家族葬を選択する際は、故人との関係性や周囲の方々の気持ちにも配慮し、誰に伝えるか、事後報告をどうするかなどを事前に検討しておくことが大切です。
- 香典が集まらないのでやりくりが大変: 低予算で執り行うことができる家族葬ですが、香典が集まらないのでやりくりはそれなりに大変という話もよく聞かれます。故人が生前あちこちの葬儀に参列していた場合、「赤字」になるといった声も。
葬儀の準備としてやっておきたいこと
「もしもの時」に慌てず、後悔のない葬儀を執り行うために、生前から準備できることはたくさんあります。
- 自分の希望する葬儀の形式を明確にしておく: 一般葬、家族葬、一日葬、直葬、オンライン葬儀など、どのような形式が良いかを考えてみましょう。
- 葬儀社の資料を取り寄せて比較してみる: 複数の葬儀社のパンフレットやウェブサイトを確認し、提供されるサービスや費用、会社の理念などを比較検討します。
- 費用の目安や準備すべき金額を確認しておく: 葬儀の形式によって費用は大きく異なります。おおよその費用感を把握し、無理のない範囲で準備できる金額を検討しましょう。
- 喪主にお願いしたい人、呼んでほしい人を書き出しておく: 誰に喪主をお願いしたいか、そして葬儀に参列してほしい人をリストアップしておきましょう。
- 遺影や思い出の写真を用意しておく: 生前の姿を偲ぶ遺影や、故人の人柄が伝わる思い出の写真は、葬儀をよりパーソナルなものにしてくれます。
- 宗教・宗派、戒名の希望、納骨先の相談: 宗教や宗派の有無、希望する戒名、納骨先の希望など、具体的な事項も家族と相談しておきましょう。
- エンディングノートに記載、または家族に口頭で伝えておく: 準備した内容をエンディングノートにまとめたり、家族に直接伝えたりすることで、確実に希望を伝えられます。
生前遺影の準備もお早めに
 人生の終末について考える中で、意外と後回しにされがちなのが「遺影」の準備です。なかには「縁起でもない」なんて思っているひともまだいらっしゃるかも。しかし、生前遺影は、あなたが確かに生きた証であり、その人生における尊厳を象徴するものと言えるでしょう。
人生の終末について考える中で、意外と後回しにされがちなのが「遺影」の準備です。なかには「縁起でもない」なんて思っているひともまだいらっしゃるかも。しかし、生前遺影は、あなたが確かに生きた証であり、その人生における尊厳を象徴するものと言えるでしょう。
元気なうちに、自分らしい最高の笑顔や、お気に入りの場所で撮影した写真を生前遺影として準備することは、自己肯定感を向上させる効果も期待できます。「こんな素敵な写真が遺されたら、この人生まんざらでもなかった」「みんな、きっと喜んでくれるだろう」という想いは、残りの人生をより積極的に生きる活力にも繋がるかもしれません。
そして何より、あなたが大切に思うご家族にとって、素敵な遺影写真があることは、突然の別れの悲しみを乗り越える上で大きな慰めとなります。あなたの笑顔が、いつまでも家族の心に寄り添い続けるでしょう。
故人を偲ぶ、温かい演出のアイデア
葬儀は、故人の人生を振り返り、感謝の気持ちを伝える大切な機会です。故人らしさを表現し、参列者の心に残るような温かい演出を取り入れてみてはいかがでしょうか。
- 思い出のBGM: 故人が生前好きだった音楽や、人生の節目に流れていた思い出の曲などを葬儀中に流すことで、故人を偲ぶ空間を演出できます。故人の人となりを表すような明るい曲や、心安らぐような静かな曲を選ぶのも良いでしょう。著作権などの関係で利用できる楽曲が限られる場合もあるため、事前に葬儀社に相談することをおすすめします。
- 感謝のビデオメッセージ: 生前に故人から家族や友人へ宛てたビデオメッセージを上映することも、心温まる演出となります。直接言葉で伝えられなかった感謝の気持ちや、思い出のエピソードなどを語ることで、参列者の感動を誘い、故人をより身近に感じることができます。撮影や編集は、自分で行うだけでなく、葬儀社に依頼できる場合もあります。
- メモリアルコーナー: 故人の写真や愛用品などを展示するメモリアルコーナーを設けるのも良いでしょう。故人の趣味に関するものや、旅行先で集めたお土産などを飾ることで、故人の人となりを偲ぶきっかけとなり、参列者同士の思い出話にも花が咲くかもしれません。
- 献花・メッセージ: 従来の焼香の代わりに、故人が好きだった花を献花したり、メッセージカードに故人への想いを綴って供えたりする形式も、故人を偲ぶ新しい形として広がっています。参列者一人ひとりが故人を想う時間を持つことができ、心温まる雰囲気を作り出すことができます。
これらのアイデアはあくまで一例です。故人の個性や遺族の意向に合わせて、様々な工夫を取り入れることができます。葬儀社の担当者と相談しながら、故人らしい、心に残るお見送りを実現してみてはいかがでしょうか。
⚠️ 身内が亡くなった後、残された時間は少ない!
残念ながら、身内が亡くなった後は、数時間のうちに葬儀社を選定し、葬儀の手配をしなければならないのが実情です。 病院で亡くなった場合、霊安室に安置できる時間は限られており、多くの場合、すぐに葬儀社に搬送をお願いする必要があります。
悲しみの中で冷静な判断をするのは非常に困難です。故人の意思が不明確なままだと、残されたご家族は、限られた時間の中で多くの選択を迫られ、大きな精神的負担を抱えることになります。
このような状況を避けるためにも、事前の準備がいかに重要であるか、改めて認識しておく必要があります。
葬儀社は事前に見学して回りましょう
パンフレットやWEBサイトの情報だけでは分からないこともあります。葬儀社の雰囲気や担当者の対応は、実際に足を運んでみないと分からないものです。
複数の葬儀社とイベントを共催した経験からも、企業によって社風や社員教育の隅々に至るまで大きな違いがあることを実感します。葬儀社を選ぶ際には、単に「優れているか」「見積り金額はどうか」という視点だけでなく、ご自身やご家族の感覚に合っているかを見極めることが大切です。
- 担当者の言葉や対応: 親身になって相談に乗ってくれるか、こちらの疑問や不安に丁寧に答えてくれるかなどを確認しましょう。
- 社風: 会社全体の雰囲気が、自分の求める「お別れの場」のイメージに合っているかを感じ取ることが大切です。
- 設備: 式場や安置室、控室などの設備が清潔で、必要なものが揃っているかなども確認しておくと安心です。
新しい葬儀スタイルを検討する際のポイント
特に、一日葬のような新しい葬儀スタイルを検討する際は、僧侶の手配などもよく確認のうえ執り行うことが肝心です。従来の形式とは異なるため、僧侶の手配や読経の時間、式の進行など、細かな調整が必要になる場合があります。
その際、葬儀社の担当者が新しい形式にも慣れており、しっかり対応できるかどうかが、円滑な葬儀を行う上での重要な判断基準となります。事前にその点も確認し、安心して任せられる葬儀社を選びましょう。
いくつかの葬儀社を実際に訪れることで、納得のいく選択ができるでしょう。できれば元気なうちに、複数社を比較検討し、信頼できる葬儀社を見つけておくことを強くお勧めします。
イベント等を熱心に開催している企業の担当者の話を聞けると、いろいろと見落としていることに気付かされるかもしてません。
自分の意志があることで家族が救われる
葬儀の準備をしておくことは、決して縁起でもないことではありません。
突然の別れの中で、「どうしてあげたらよかったのだろう」と迷いながら葬儀を進めるご家族が、どれほど多いことでしょうか。でも、生前に故人の意思が明確であれば、
「本人がこう言っていたから」
「これが希望だったから」
と確信を持って送り出せると思うのです。それは遺された人にとって大きな安心となり、故人を偲ぶうえでの支えにもなります。
「自分らしさ」を大切にしたい方へ
演出のアイデアでも触れましたが、生前に好きだった音楽を流す、趣味の品を飾る、生前の写真をスライドで流す…。葬儀は単なる儀式ではなく、「感謝を伝える場」であり、「人生を語る場」でもあります。
「自分らしい最期を迎える」という視点で、少しずつ準備してみませんか?終活とは、最後まで自分の人生を生き切るための活動です。その一歩として、葬儀のことも見つめ直してみましょう。
ご自身の葬儀について、もし具体的なイメージが湧かない場合は、まずはどのような「お別れ」を望むか、家族と話し合ってみることから始めてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人

- 今井 賢司終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)