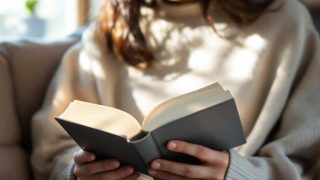2025年導入予定!オンラインでできる公正証書遺言のメリットとは?
 2025年内に日本の遺言制度に大きな変化が訪れます。
2025年内に日本の遺言制度に大きな変化が訪れます。
これまで公正証書遺言の作成は、公証人と対面で手続きを行う必要がありましたが、これからはオンラインで手続きができるようになります。
「遺言はまだ先の話」と感じている方も、「遺言は必要だが何かと面倒で」と考えている方も、この新しい制度によって大切な想いをより簡単かつ確実に残せるようになるのです。
公正証書遺言デジタル化とは?
公正証書遺言は、公証人があなたの遺言内容を聞き取り、法的に有効な形で文書を作成し、原本を公証役場で保管する遺言方式です。これまでは、公証役場に直接行き、書面で手続きをする必要がありました。
しかし、2025年12月までに
-
オンライン申請が可能に
-
電子署名で本人確認ができ
-
公証人の許可があれば、ウェブ会議で内容確認や陳述ができる
-
原本は紙ではなく電子データで作成・保管され
-
正本・謄本(写し)も電子データで交付可能になる
という大きな変革が始まります。
公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について │ 法務省
公正証書遺言デジタル化のメリット
この変化によって、
-
遠方に住む方や身体の不自由な方でも公証役場に足を運ぶ負担が軽減されます。
-
書面の紛失や改ざんのリスクがほぼなくなります。
-
書類作成や交付のスピードがアップし、手続きが格段に簡単になります。
特に宇都宮市のように、公共交通が発達しているとはいえ、忙しい方や高齢者にとっては大きな助けになるでしょう。
そもそも遺言って何?
遺言とは、あなたが亡くなった後に「財産を誰に何を残すか」という希望を伝える法的な文書です。
「遺言なんて特別な人だけの話」
そう思っていませんか?
実は、多くの方が「自分には関係ない」と感じている間に、突然の相続問題に直面しています。
相続は「家族の争い」になることも少なくありません。
なぜ遺言が必要?
昔は家制度が強く、長男が家を継ぐのが当たり前でした。
しかし現代は、
-
家族の形が多様化し、離れて暮らす人も増え
-
再婚や内縁関係も増加し
-
相続人の範囲も複雑に
なっています。
遺言がないと、法律で決められた「法定相続分」に従って財産が分けられますが、
それが家族の事情や希望と合わず、トラブルになることが多いのです。
知っておきたい!日本の遺言の3つの方式
自筆証書遺言
全文を自分で手書きし、日付・署名・押印をする方式です。
メリットは費用がほとんどかからず手軽なこと。
デメリットは、書き方が法律で厳しく決まっているため、誤りがあると無効になるリスクがあることと、保管が自己責任になることです。
近年は財産目録をパソコンで作成できるようになり、法務局に保管を依頼できる制度もできて安全性が高まりました。
公正証書遺言
公証人があなたの口述する遺言内容を確認して作成し、公証役場が原本を厳重に保管します。
作成には手数料がかかりますが、
-
形式不備で無効になるリスクがほぼなく
-
家庭裁判所の検認(遺言の有効性確認手続き)が不要
という安心感があり、法律の専門家からも推奨されています。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言書の存在」を証明してもらう方式です。
利用は少なめで、あまり一般的ではありません。
遺言の現状と相続トラブルが教えてくれること
「争族」は他人事ではない
日本では、まだまだ多くの人が遺言書を作成していません。
法務省のデータによると、令和元年の時点で、自筆証書遺言は約17万件、公正証書遺言は約7万件と、全体としてみれば遺言書を用意している人はまだまだ少数派なのです。
とくに70歳以上の高齢者層で遺言書の作成が増えているものの、社会全体でみると「遺言がまだ身近なものになっていない」というのが実情です。
しかし一方で、相続がきっかけで家族が争う「争族」の話題は決して珍しくありません。
内閣府の調査では、相続に関して何らかのトラブルを経験した家族が約7%もいるという結果が出ています。トラブルにまでは発展しないものの、内心嫌な思いをしたり関係性が悪化するといった潜在的な不満はもっと多いのではないかと私はみています。
それは、遺言書がなかったり、内容が不明確だったり、または見つからなかったりすることが原因で、遺産分割の話し合いが難航し、家族の絆が壊れてしまうケースが多いのです。
さらに、自筆証書遺言の場合は保管場所がわからず見つからない、あるいは偽造の疑いがかかるなどして、家庭裁判所での検認という手続きが必要になることもあります。
こうした現状を踏まえると、遺言は「自分の財産をどうするか」というだけの問題ではなく、残される家族の心の平安を守るために、早めにしっかり準備しておくべき大切な“家族への最後の思いやり”と言えるでしょう。
米国での進んだ遺言事情とその背景
米国では、成人の半数以上が遺言書を作成していると言われており、日本に比べて遺言の準備が進んでいる社会です。特に若いうちから遺言書を作成することも珍しくなく、人生設計の一環として早期の準備が浸透しています。
この背景には、遺言書を通じて自分の意思をしっかり伝え、家族に無用な争いを起こさせないための文化的な理解が根付いていることがあります。
さらに、米国では法律の複雑さや州ごとに異なる相続ルールを踏まえ、専門家のアドバイスを得ながら遺言を整備することが一般的で、オンラインサービスなどITの活用も進んでいます。
こうした積極的な遺言作成の取り組みは、家族の安心や円滑な財産承継につながり、多くの人が「終活」として遺言を活用しているのです。
日本でも公正証書遺言のデジタル化が進むことで、米国のように遺言がより身近で気軽なものになり、人生設計に取り入れやすくなることが期待されます。
デジタル化された公正証書遺言の活用ポイント
1. 早めの作成が身近に
デジタル化で手続きが簡単になるため、元気なうちから作っておけるようになります。何度でも更新ができるので、ライフステージに合わせて内容を変えることも可能です。
2. 遠方に住む家族との意思疎通がスムーズに
ウェブ会議で遺言の内容確認や意思表示ができるため、宇都宮を離れて暮らす家族も安心して関われます。
3. 紛失や改ざんの心配が減る
電子データとして公証役場が保管するので、紙のように紛失や改ざんされるリスクがほぼありません。
🏛 栃木県内の公証役場と法務局の連絡先
公証役場(公正証書遺言の作成)
-
宇都宮公証役場
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡1丁目1-26 小幡ビル2階
TEL:028-624-1100
※公正証書遺言の作成には、予約が必要です。
法務局(自筆証書遺言の保管)
-
宇都宮地方法務局
〒320-8515 栃木県宇都宮市小幡2丁目1-11
TEL:028-623-6333
※自筆証書遺言の保管制度の詳細や手続きについては、事前にお問い合わせください。
デジタル化が遺言のハードルを下げる
公正証書遺言のデジタル化は、これまで「面倒で難しい」と感じていた終活のハードルを大きく下げるチャンスです。また、自筆証書遺言のデジタル化も検討されているそうです。
ただし、どんなに便利になっても、遺言は「あなたの想い」を未来に届ける大切なメッセージ。デジタル化によって手続きの選択肢が増え、利便性を高めるというだけで、遺言の本質は何も変わるものではありません。
相続トラブルを防ぐだけでなく、残された家族への感謝や思いやりを込めて作成してください。
終活を考えている方はこの新制度を上手に活用し、安心できる未来を準備しましょう。
※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)