「負動産」を相続しないために──空き家・使わない土地があなたを苦しめる前に
「負動産」は他人事じゃない時代へ
日本の高齢化と人口減少は、地域社会の姿を根本から変えつつあります。その象徴的な問題が、空き家や利用予定のない土地の増加──いわゆる「負動産」の存在です。
国土交通省の「住宅・土地統計調査(2023年10月)」によると、全国の空き家数は約900万戸。住宅全体の13.8%に達し、今後も増加が予測されています。特に、地方や郊外では過疎化とともに「売れない・貸せない・管理ができない」不動産が広がり、資産どころか負担となるケースが少なくありません。
こうした背景のなか、「不動産=資産」という価値観は見直しを迫られています。
- 前回・2018年調査(849万戸、空き家率13.6%)と比べ、+51万戸・率は+0.2ポイント増で、引き続き増加傾向
- 増加のペースは加速しており、過去30年で約2倍に拡大
- 空き家のうち、「賃貸・売却・別荘用途を除く放置空き家」は約385万戸(全体の約43%)。その多くが築古・倒壊リスクありと分類され、より深刻な状態に
相続したくないのに責任は残る
所有者としての義務とリスク
 不動産は、相続したくないからといって放置しておけるものではありません。所有し続ける限り、次のような負担と責任が発生します。
不動産は、相続したくないからといって放置しておけるものではありません。所有し続ける限り、次のような負担と責任が発生します。
-
固定資産税の支払い
-
草木や雑草の管理
-
建物の老朽化による倒壊リスク
-
第三者への損害賠償責任
さらに、適切な管理を怠ると「特定空き家」に指定され、固定資産税の軽減措置が解除されるうえ、行政代執行による解体・撤去費用を請求されることもあります。
■「特定空き家」に指定されるとどうなる?
- 「倒壊など著しく保安上危険な状態」などと判断された空き家が対象
- 市区町村から改善命令が出され、従わない場合は行政代執行による強制解体も
- 従来の空き家と異なり、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6)が解除され、税負担が6倍に
- 管理責任者に解体・修繕費が請求されるケースもあり、相続人にも影響が及ぶ
- 2023年度末時点で、全国で1万件超が「特定空き家」指定済み(国土交通省調べ)
▶ 放置すればするほどリスクとコストが増すため、早期の対応が不可欠です。
古い建物に潜む修繕リスク
見えないコストが資産価値を下げる
築年数の古い建物は、耐震基準の不適合や雨漏り・配管トラブルなど、修繕費が高額になるリスクを抱えています。
特に、以下のような物件は買い手から敬遠されがちです。
-
エレベーターのない高層階物件
-
旧耐震基準(1981年以前)で建てられた建物
-
リフォーム前提の築古住宅
買い手がつきにくく、結果的に売却もままならず、「売れない資産」が「負動産」へと変化してしまいます。
よくあるトラブル・リスク
-
放置空き家が近隣トラブルに発展
倒壊や雑草、害虫の発生で、近所からクレームや行政指導が入ることも。 -
相続税や管理費がかさむ
使っていなくても、固定資産税や管理費は発生。空き家特例の対象外になると税額が大幅に増えることも。 -
売却や譲渡が難航
「タダでもいらない」と言われるケースも。解体・整地費用を払ってようやく引き取ってもらえる場合もあります。 -
相続トラブルに発展
複数人で相続したが誰も管理せず、兄弟姉妹で揉めることも。
立地や周辺環境の変化にも要注意
バイパスや再開発で価値が激変することも
都市再開発やインフラ整備の影響で、人の流れが変わることもあります。かつては集客の見込めた商業地が、新たな道路の開通で人通りが激減──そんな例も少なくありません。
たとえば、
-
旧市街地にあるテナントビル
-
路線バスの廃止に伴い利用者が減った月極駐車場
こうした物件は収益性を失い、修繕費や管理費だけが残る典型的な「負動産」と化してしまいます。
将来の相続に備えて検討すべき対処法
不動産が「資産」から「負担」に変わる前に、以下のような具体的対策を取っておくことで、相続トラブルや金銭的リスクを未然に防ぐことができます。
相続放棄──「引き継がない」という選択肢
相続開始後、3か月以内であれば家庭裁判所に申し立てを行い、相続そのものを放棄することが可能です。
負債だけでなく、管理困難な不動産を避けたい場合の最後の手段ですが、他の財産もすべて放棄することになるため注意が必要です。事前に財産の全体像を確認しておくことが不可欠です。
空き家バンクの活用──地域との橋渡しによる利活用
自治体が運営する「空き家バンク」に登録すれば、地域への移住希望者やリノベーションを希望する若年層とのマッチングが期待できます。
価格は低くなりがちですが、社会貢献にもつながる選択肢です。登録には建物の現況報告書や耐震診断が求められる場合があるため、書類の準備は事前に行いましょう。
国庫帰属制度──国に引き渡す制度の新設(2023年施行)
不要な土地を国に引き渡すことができる制度で、2023年に始まりました。
ただし、対象となる土地には「更地であること」「境界が明確」「担保権や通行権がない」など厳しい条件があり、事前に整備が必要です。また、負担金(10万円〜数十万円)も発生します。
売却・寄付・一部賃貸などの柔軟な選択肢
売却が難しい物件であっても、条件付き売却(例えば更地にしてから売る)や、NPO団体・町づくり法人への寄付、部分的な賃貸活用といった方法が検討できます。
不動産会社によっては「訳あり物件」専門の業者もあり、再販や投資向けとしての活用も視野に入ります。
専門家への早期相談──「自分だけで判断しない」ことが鍵
司法書士や行政書士、不動産鑑定士などに早い段階で相談しておくことで、相続発生後の混乱を避けることができます。
自治体によっては無料の空き家相談窓口や、ワンストップの支援制度を設けているところもあるため、まずは地元の行政サービスを調べることをおすすめします。
相続登記の義務化が始まりました(2024年4月〜)
不動産を相続したら、これまでは登記が「任意」でしたが、2024年4月からは相続登記が義務化されました。これにより、所有者不明の土地や空き家の増加を防ぐ狙いがあります。
■ 相続登記義務化のポイント
- 相続を知った日から3年以内に登記を申請することが義務
- 遺産分割協議が未了でも、法定相続分での登記申請が可能
※後日遺産分割協議で異なる内容の登記をすることになった場合、再度登記手続きが必要になる可能性があります - 正当な理由なく登記を怠ると、5万円以下の過料の対象になる場合も
- 2024年4月1日以前の相続にも適用され、未登記の不動産には今後対応が必要
なぜ義務化されたのか?
これまで、相続登記がされずに放置された土地・建物が多数存在し、「所有者不明土地」が全国で九州本島の面積に匹敵する規模にまで拡大(国交省試算)。公共事業や災害復旧に支障が出るなど、社会問題化していました。
相続=登記ではないことに注意
実は、遺産分割が終わっていても、法務局に登記申請をして初めて「名義変更」が成立します。登記しないままだと、売却も貸し出しもできず、後々の相続でもトラブルの火種になりかねません。
✔ この記事を読んで「まだ登記していない」不動産が思い浮かんだら…
一度、自宅や実家の名義がどうなっているか、法務局や司法書士に確認してみることをおすすめします。
相続登記を放置していると、「負動産」がさらに複雑化するリスクがあります。
不安や疑問がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。以下は主な相談先です。
- 法務局の「不動産登記相談」 → 登記手続きや必要書類について無料相談可(事前予約制) ▶ 法務局公式サイトはこちら
- 司法書士会の無料相談窓口 → 各都道府県で実施。登記や相続手続きの初回相談が可能 ▶ 日本司法書士会連合会サイト
- 市区町村の「空き家対策窓口」 → 空き家バンク、補助制度、解体支援なども含めた包括的な相談可
▶宇都宮市生活安心課空き家・空き地対策グループ 電話: 028-632-2266
▶宇都宮空き家会議
世代を超えて考える「資産のあり方」

家族で「負動産」について話すということ
負動産の問題は、家族の問題でもあります。
「子どもには迷惑をかけたくない」と思うならこそ、この先どのように扱うかを考えることが大切な終活です。
-
実家はどうする?
-
誰が管理する?
-
使わないなら処分する?
-
将来、誰かが住む予定はある?
こうしたことを家族で共有しておくことで、将来の相続トラブルや負担を大きく減らすことができます。
今後、親の不動産を相続することになるミドル世代。そして、自分の不動産を子に残そうと考えるシニア世代。双方にとって、「不動産は誰のために・何のために持つのか?」を問い直す時代です。
所有することがリスクとなる時代に、「いかに手放すか」を考えることもまた、賢い資産管理のひとつです。将来の相続人に悩みを残さないためにも、今こそ対話と準備を始めてみませんか?
※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰 兼 栃木支部長。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催します
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)
 相続2025年8月28日「負動産」を相続しないために──空き家・使わない土地があなたを苦しめる前に
相続2025年8月28日「負動産」を相続しないために──空き家・使わない土地があなたを苦しめる前に コラム2025年8月21日お見舞いのマナー完全ガイド|服装・持ち物・快気祝いまで丁寧に解説
コラム2025年8月21日お見舞いのマナー完全ガイド|服装・持ち物・快気祝いまで丁寧に解説 親の終活2025年8月7日親の終活を考える ―― 理想的な終活は、家族とともに歩むもの
親の終活2025年8月7日親の終活を考える ―― 理想的な終活は、家族とともに歩むもの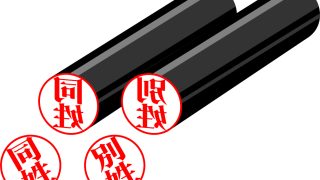 コラム2025年7月31日夫婦別姓と終活――「家」を超えても、「家」から離れられない ――
コラム2025年7月31日夫婦別姓と終活――「家」を超えても、「家」から離れられない ――

