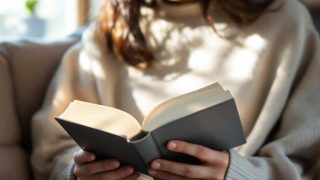認知症はまだ先の話?──“その時”に備える終活のすすめ
認知症への備えも、大切な終活
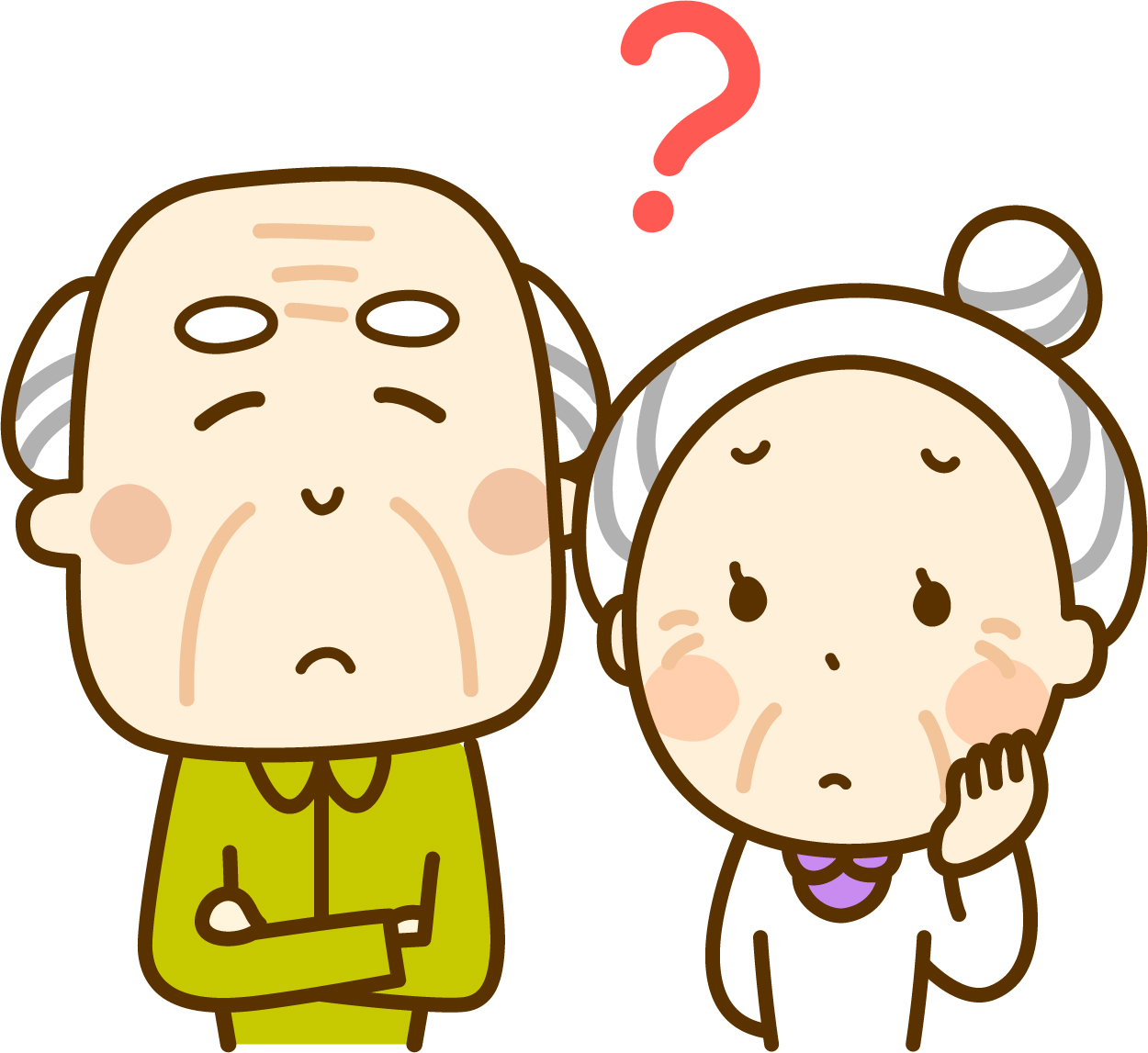 いま、「2025年問題」が現実のものとなり、私たちの社会に大きな影響を与えています。
いま、「2025年問題」が現実のものとなり、私たちの社会に大きな影響を与えています。
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となるこの2025年、認知症の高齢者数は約700万人に達し、65歳以上の7人に1人が認知症になると推計されています。さらに、軽度認知障害(MCI)などの予備軍を含めると65歳以上の4人に1人が認知症に関係する状態にあるとも言われており、認知症は誰にとっても起こり得る症状であり、無関係ではいられない深刻な社会課題です。
認知症は、年齢を重ねる中で多くの人にとって身近な問題となりつつあります。65歳を過ぎると、誰でも認知症になってもおかしくないという現実があります。そして、認知症が進行すると、今後のことを決定することが難しくなり、周囲の人々に負担をかけることにもなりかねません。財産の処分や遺言書の作成ができず、銀行口座が凍結される可能性も出てきます。また、本人の医療や介護に関する希望も、周囲にはわからなくなってしまうことがあります。そのため、認知症に備えることは、あなた自身と家族を守るための大切な終活となります。
認知症が進行すると起こる可能性のあるトラブル
認知症が進行すると、以下のような問題が起こることがあります。
財産の管理ができなくなる
認知症が進行すると、銀行の通帳やキャッシュカードの管理が難しくなり、銀行口座が凍結される可能性があります。これにより、家族であっても自由に出金や支払いを行うことができなくなります。
また、配偶者居住権が設定されている場合でも、配偶者本人が認知症を発症すると、自宅を売却して介護費用に充てるといった判断が難しくなり、資産の流動化が困難になるという新たな問題も発生します。
遺言書が書けなくなる
判断力が低下すると、有効な遺言書を作成することができなくなり、望んだ通りに財産を分けられなくなります。
医療や介護の意思表示が困難になる
延命治療や施設入所の希望を伝えられなくなり、最終的に家族が意思決定をしなければならなくなることがあります。
詐欺に遭うリスクが増える
高齢者は詐欺や悪徳商法のターゲットになりやすく、大金を無駄に使ってしまうことがあります。
認知症が疑われる兆候
以下のような変化が見られたら、認知症の初期兆候かもしれません:
- 日常的な記憶の欠落(最近の出来事や名前を忘れる)
- 時間や場所がわからなくなる
- 繰り返し同じ質問をする
- 会話が続かない、言葉が思い出せない
- 部屋が散らかり始めた
- 物を置き忘れたり、物の所在がわからなくなる
- 自分のことや他人のことを誤って認識する
- 財布に小銭がパンパンに入っている(計算ができなくなり、札で支払い、小銭をためこんでしまう)
認知症の症状の変動と診断の難しさ
 認知症は症状が一様に進行するわけではなく、本人の覚醒状態や環境の影響で症状が変動します。時には記憶がはっきりしている時期と、混乱している時期を行き来することもあります。
認知症は症状が一様に進行するわけではなく、本人の覚醒状態や環境の影響で症状が変動します。時には記憶がはっきりしている時期と、混乱している時期を行き来することもあります。
また、認知症の診断時に緊張や不安で一時的に覚醒してしまい、本来の症状が見えにくくなることも少なくありません。
こうした症状の波は、本人や家族、医療者にとっても判断を難しくし、対応を慎重にしなければならない重要なポイントです。認知症の理解には、こうした「変動する症状」の特徴を知ることが不可欠です。
認知症をめぐる社会的課題
認知症は、本人や家族がすぐに気づけるとは限りません。見逃したり、対応が遅れてしまう背景には、暮らしや社会のあり方が大きく関わっているのです。
ソロ社会化による孤立
一人暮らしの高齢者が増え、身近に相談できる家族や知人がいないと、認知症の初期症状に気づくのが遅れる傾向があります。
地方での医療・介護体制の不足
地方では認知症の専門医や介護サービスが十分に整っていない地域も多く、早期診断や適切な支援が受けにくい状況があります。
認知症への偏見や誤解
「認知症は怖い」「介護は大変」などのネガティブなイメージが根強く、本人や家族が相談をためらう原因となっています。
軽視や誤認の問題
「年のせい」「物忘れは大したことない」と思い込み、認知症の兆候を見逃してしまうことも多く、早期の対策が遅れがちです。
認知症への備えを考えるうえで、こうした社会背景は知っておきたいポイントです。現実を理解することが、本人にも家族にも、向き合う力を与えてくれます。
認知症は、症状が日によって異なり、覚醒している時間帯には普通に見えることもあります。実際、認定のときに限って受け答えがはっきりしていて、本来の状態が正しく評価されなかったというケースも珍しくありません。
そうした事態を防ぐためには、日頃の様子を記録したメモや、可能であれば動画での記録などが、医師やケアマネジャーに状態を伝える手がかりとして非常に有効です。
家族や周囲の観察と記録が、的確な支援や診断へとつながります。
認知症が疑われたら、まず相談したい窓口
早めの対応が、本人と家族の安心につながります。認知症が疑われたら、以下のような窓口に相談してみてください。
地域包括支援センター
高齢者の暮らしを支えるために各市町村に設置されている公的な相談窓口です。介護、医療、福祉、権利擁護などの分野にまたがる支援を、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門職がチームで行っています。
「まだ介護保険を使うほどではない」「ちょっと気になることがある」という段階でも相談でき、認知症に関する不安や今後の備えについても、適切な窓口や支援につないでくれます。
余談ですが、私は父の終末期において、地域包括支援センターのスタッフさんのアドバイスにより、救急搬送の適切な判断ができた経験があります。医療介護の判断は尻込みしがちですが、専門家の助言を仰ぐことで客観的に判断できることもあります。
オレンジドクター(認知症サポート医)
認知症に関する専門的な知識をもつ医師が、本人や家族、地域の医療・福祉関係者を支援します。地域包括支援センターを通じて紹介してもらえます。
一人暮らしや地方の暮らしでは目立ちにくい初期症状も、相談医が地域での架け橋となり、早期発見・対策への窓口となります。
栃木県もの忘れ・認知症相談医(とちぎオレンジドクター)登録者名簿(PDF 2025年5月時点)
(県庁サイトから誰でも閲覧・ダウンロード可能です)
また、制度の概要や名簿へのアクセス方法は、こちらの案内ページにも記載されています:
「栃木県もの忘れ・認知症相談医(とちぎオレンジドクター)について」
認知症サポーター養成講座について
 地域で認知症の方とその家族を支える力として、「認知症サポーター」の存在があります。全国各地で行われている認知症サポーター養成講座では、認知症の正しい知識と接し方を学ぶことができます。市町村の広報紙にもよく掲載されていますね。
地域で認知症の方とその家族を支える力として、「認知症サポーター」の存在があります。全国各地で行われている認知症サポーター養成講座では、認知症の正しい知識と接し方を学ぶことができます。市町村の広報紙にもよく掲載されていますね。
私たち終活サポート ワンモアでも、地域包括支援センターのご協力をいただきながら、この養成講座を開催した実績があります。多くの市民の方々が参加され、地域全体での支え合いの輪が広がっています。
「気のせいかもしれない」「加齢のせいだろう」「もう少し様子を見てからでも…」と、迷いや逡巡が生じやすいのが現実です。特に、本人が一時的にしっかりしていると、周囲も安心してしまい、対応が遅れるケースも少なくありません。
しかし、その「様子見」が事態を悪化させることもあります。判断力が残っているうちにこそ、必要な手続きを行ったり、希望を確認することができるからです。認知症の初期対応が早ければ、症状の進行を遅らせたり、生活の質を保ちながら支援を受ける道も開かれます。
「もしも」の段階でこそ、相談することは決して早すぎることではありません。
今できる備えが、未来を守る
 認知症になってからでは、できることが限られてしまいます。
認知症になってからでは、できることが限られてしまいます。
だからこそ、「まだ元気なうちに」備えておくことが、あなた自身の安心につながり、大切な人たちを守ることにもなります。
終活は、死に向かう準備ではなく、“これからをより良く生きるための準備”です。
認知症への備えも、立派な終活。認知症になっても、私たちは生きていかなければならないのですから。
※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)