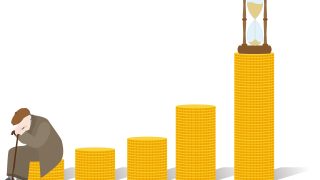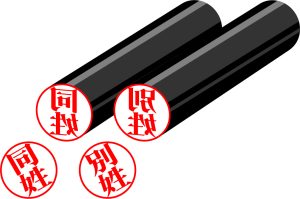親の終活を考える ―― 理想的な終活は、家族とともに歩むもの
親の終活に寄り添う難しさ
「親に終活をさせたい」のは家族のエゴだと気づいた
私のことを「写真館の跡継ぎ」だと思っている方も多いのですが、実は私の父は消防職員でした。
父は2歳のときに実父を亡くし、幼い頃から母(=私の祖母)の商売を手伝いながら苦学してきた苦労人でした。苦労自慢をするようなこともなく、謙虚で実直な人柄は私にとって尊敬すべき父親でした。
一方で、私は写真という世界に憧れを抱き、やがてそれを生業に選びました。
そんな私の生き方や職業観に、父はなかなか理解を示してくれず、衝突することもしばしばありました。困難が予想される専門性の高い世界で、世間知らずな我が子に苦労をさせたくないという親心だったと思っています。
独立後、わずかに仕事を認めてくれるようになったと感じたこともありましたが、「生前遺影」は、なかなか撮らせてはもらえませんでした。
私は写真館の経営の傍ら、終活カウンセラーとしても活動しており、生前遺影の大切さを多くの方に伝えてきた立場です。
そんな自分が、身内である父の遺影を生前に撮影できていない――そのことは、ずっと心の片隅に引っかかっていました。
ですが、終活支援の活動を続けるなかで、次第にそれは「私のエゴではないか」と思うようになりました。
終活とは、誰かに「させる」ものではなく、本人の悩みや思いに寄り添い、その解決を支えること。
生前遺影も押しつけるのではなく、プロとしての意見を伝えつつ、あくまでご本人のタイミングを大切にする――そんな関わり方こそ、本当の終活支援ではないかと考えるようになったのです。
 その後、父は長年患っていた癌の治療のため、抗がん剤を始める直前になって、ようやく私に生前遺影の撮影を託してくれました。
その後、父は長年患っていた癌の治療のため、抗がん剤を始める直前になって、ようやく私に生前遺影の撮影を託してくれました。
実家の庭で、両親を並べて撮影したその時間は、束の間でしたが私にとって忘れがたいひとときとなりました。
父はとても縁起を担ぐ人で、実兄(私の伯父)が墓の手直しをした直後に心筋梗塞で急死した経験もあり、それが遺影を避ける気持ちに拍車をかけていたのだと後から知りました。
また、長く病気を抱えていたこと自体も、お互い生前遺影の話を切り出しにくくしていた理由のひとつでした。
私は、無理に撮らなくて本当に良かったと今では心から思っています。
父の遺影写真撮影については別のブログにて詳細に書いています。よろしければご一読ください。
静かに始まっていた“父の終活”
その一方で、後からわかったことですが、父は亡くなる数カ月前から自分の保険の書類を整理していたようでした。何事にも几帳面な人でしたが、自身の身体の異変をうすうす感じていたのかもしれません。
 また近年、古いアルバムを整理し、新しいポケットアルバムにお気に入りの写真を収めていたようです。時系列ではなく、色々な時期の写真がランダムに並んでいて、その点几帳面な父らしくないアルバムでした。きっと時間がなかったのでしょう。どんな想いでそれらを整理していたのかと思うと、今でも胸が締め付けられます。
また近年、古いアルバムを整理し、新しいポケットアルバムにお気に入りの写真を収めていたようです。時系列ではなく、色々な時期の写真がランダムに並んでいて、その点几帳面な父らしくないアルバムでした。きっと時間がなかったのでしょう。どんな想いでそれらを整理していたのかと思うと、今でも胸が締め付けられます。
一昨年の夏、庭で採れたプラムを実家に届けたときのこと。「美味いなあ」と両親が喜び、父が「うちも植えようかな」と言いました。私は「3年もすれば実が採れるよ」と答えると、父がふと「3年か…」と呟き、少し沈黙が流れました。言葉はなくとも何を思ったのかは明白でしたが、それから3年を待たずに父は他界。そのすぐ後に植えたプラムは、この夏もまだ実をつけませんでした。それでも、希望を抱いて植えられたプラム、ふと目にするその木に時間の重みを感じます。
無理強いはしないと決めていたぶん、父の終活には深く関われないまま終わってしまいました。でも、何かしら別の形で寄り添うことができたかもしれません。
親の選択を尊重した終活。正解はないのかもしれませんが、その判断は間違いではなかったと思う一方で、小さな後悔も残っています。
最近、「親の終活をどう進めたらいいでしょう?」とご相談を受ける機会が増えています。
理想的な終活とは本人が一人で取り組むものではなく、家族や親しい人たちとともに歩んでいくプロセスだと私は思っています。
実際に、内閣府の高齢社会白書(令和6年版)によると、65歳以上の高齢者のうち、「自分の死後について準備をしている」と答えた人は約3割程度にとどまり、多くは「考えなければと思いながらも、まだ何もしていない」と回答しています。
家族や周囲の人が「まだ元気だし、今じゃなくても」と考えてしまいがちな現実が、こうしたデータにも現れています。(※参考:内閣府「高齢社会白書」令和6年版 )
親世代が終活に後ろ向きな理由と、その向き合い方
実際のところ、多くの親世代は「終活」という言葉に対して抵抗感を持っています。
それは、終活が「死の準備」と受け取られがちだからです。
自分がもう“終わりに近づいている”と認めたくない。
あるいは、“縁起でもない”と拒絶する。
そうした反応は決して珍しいことではありません。
さらに、彼らの中には「迷惑をかけたくない」と思う一方で、「まだ元気なうちは考えたくない」「そのうち何とかなるだろう」と考える人も少なくありません。
年齢を重ねることで、心身の衰えや認知の変化も加わり、「面倒」「難しい」「恥ずかしい」と感じることが積み重なり、結果として終活への第一歩が遠のいてしまうのです。
このような背景を理解せずに、「やっておいたほうがいいから」と子ども世代が正論で迫っても、かえって心を閉ざされることがあります。
私も父との関わりの中で、強くそれを実感しました。
では、どうすればよいのか。
まず大切なのは、「親の終活を“手伝う”のではなく、“寄り添う”」という姿勢です。
親の思いに耳を傾け、その人が抱える不安やこだわりを尊重しながら、必要に応じて情報を提供し、選択肢を示す。
その繰り返しが、少しずつ意識を変え、行動のきっかけをつくります。
たとえば、実家の片づけをきっかけに思い出話を聞く。
写真の整理から「この一枚、いい表情だね」と声をかける。
そんな小さなやりとりが、終活への自然な導線になることもあります。
また、親の体調の変化や生活の不安が見えてきたときには、「何かあったときのために、一緒に考えておきたいな」と、家族としての気持ちを率直に伝えることも、背中を押すきっかけになります。
終活とは、“親を納得させること”ではない
終活は、親を説得して思い通りに動かすことではありません。
本人が納得し、自分のペースで取り組めるように、環境と心の準備を整えること。
それを、家族としてどう支えるか――それこそが、「親の終活」の本質なのだと思います。
少しずつ、一緒に考えていく。
時には話を戻されても、焦らず、急かさず、また一歩ずつ歩む。
親の人生に敬意を払いながら、ともに歩む終活こそが、家族にとっての“心の備え”になっていくのだと、私は信じています。
親の終活はどこから始めればいいのか――「話し合う」ことが、終活の第一歩
終活というと、遺言や財産整理、介護やお墓の話など、すぐに具体的な手続きや準備のことを思い浮かべがちです。
けれど、そうした内容に入る前にまず必要なのは、先ほどもお話したように「これからの生き方について、ゆっくり話をすること」です。
たとえば――
「もしものとき、どうしてほしいと思ってる?」
「どんな老後を過ごしたい?」
「昔から大事にしてるものって、どんなの?」
こうした問いかけは、決して“死の話”ではありません。
むしろ、その人がこれからどう生きたいかを一緒に見つめ直すための、大切な入口になります。
特に親世代にとっては、「迷惑をかけたくない」という思いが強い反面、「どうすればいいかわからない」「何から手をつければいいのかわからない」と感じていることも多いものです。
だからこそ、「ちゃんと話しておこうか」「これからのこと、少しずつ考えていこうか」と、ゆるやかな声かけから始めることが大切です。
親と終活の話をするための“きっかけ”の作り方
終活の話は、いきなり切り出すと身構えられてしまいます。会議や聴き取りのように話しても、心を閉ざしてしまうだけです。
それよりも、日常のちょっとした会話や出来事をきっかけにすることで、自然に話がしやすくなります。
たとえば、
テレビや新聞の話題から入る
例:「この前テレビで、終活特集やってたよ。お母さんはどう思う?」
自分のことを先に話す
例:「私もこの前、もしものときの連絡先まとめてみたんだ。お父さんは何か考えてる?」
親の経験をたずねる
例:「おじいちゃんのときって、どうだった? あのとき大変じゃなかった?」
身近な変化を話題にする
例:「この前、○○さんのところで急に介護が始まって…お母さんも何かあったら心配だから、考えておいた方がいいかなって」
こうした“ついで”や“雑談”の中で、親が語りやすい雰囲気を作っていくことが、終活のはじまりになります。
特に、自分の考えを押しつけるのではなく、「どう思う?」「どっちがいいかな?」と問いかける形にすると、相手も気持ちを整理しながら話すことができます。
「親の終活を進めたいけれど、何から始めたらいいかわからない」という場合には、以下のような公的機関に相談するのも一つの方法です。各地域で無料相談やセミナーなども行われています。
終活について相談できる公的機関・窓口
| 分野 | 相談先 | 内容 | リンク |
|---|---|---|---|
| 終活全般 | 地域包括支援センター | 高齢者とその家族の総合相談窓口(介護、住まい、健康、生活支援など) | お住まいの地域の支援センターへ |
| 相続・遺言 | 法テラス | 法律相談(相続、遺言、成年後見など)を無料または低額で提供 | https://www.houterasu.or.jp/ |
| 成年後見制度 | 家庭裁判所 | 判断能力が低下した場合の後見人制度などの情報 | https://www.courts.go.jp/(家庭裁判所へ) |
| お墓・供養 | お墓探しサイト「いいお墓」 | 墓地や納骨堂の選び方、霊園探しの支援など | https://www.e-ohaka.com/ |
| 消費者トラブル | 消費生活センター | 終活関連サービス(遺品整理、仏壇販売等)でのトラブル相談 | https://www.kokusen.go.jp/map/ (全国のセンター一覧) |
※終活サポート ワンモアでも終活に関する様々なご相談を承ります
終活は「話し合いの積み重ね」
 誤解されている方が多いのですが、終活とは何かを一度に片づけることではありません。
誤解されている方が多いのですが、終活とは何かを一度に片づけることではありません。
家族や周囲の人と、少しずつ、話し合い、確認していくプロセスそのものが終活です。
その積み重ねが、いざというときの心の支えになり、誰かの人生の後半を「その人らしく」支えることにつながります。
だからこそ、「いつか」ではなく、「今」始めてほしい。
今、元気なうちにこそ「これからどう生きたいか」「どう終わりを迎えたいか」を、家族で話し合ってみてほしいのです。
親の終活を考えることは、同時に自分自身の「これから」を考えることにも通じます。
その対話の先にこそ、悔いの少ない人生と、温かな見送りがあると信じています。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰 兼 栃木支部長。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催します
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)