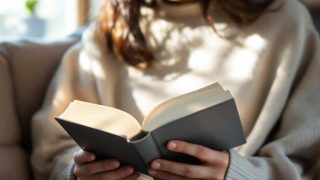認知症に備える未来へ──知っておきたい制度と支援、そして希望の兆し
認知症に関するよくある質問(FAQ)から
Q1. 認知症になったら財産はどうなりますか?
A. 判断能力が低下してから作成された遺言は無効になる可能性もあり、早めの準備が大切です。任意後見制度や民事信託などを活用しましょう。
Q2. 認知症を予防する方法はありますか?
A. 生活習慣やフレイル予防が重要です。運動、社会参加、脳トレなどが有効とされています。
Q3. 地域に相談窓口はありますか?
A. はい、各自治体の地域包括支援センターに相談できます。専門の支援員や医療チームが対応してくれます。
2025年現在、日本では65歳以上の高齢者のうち7人に1人が認知症、さらに予備軍(軽度認知障害)を含めると4人に1人が認知症の可能性があるといわれています。
もはや他人事ではなく、家族や身近な人の問題として、また将来の自分自身の課題として向き合っていく必要があります。
とはいえ、決して悲観することはありません。
早期の備えと支援制度の活用、生活習慣の見直しによって、認知症は予防も遅らせることもできる時代です。今回は、そんな備えと支援の選択肢、そして希望となる兆しについてご紹介します。
関連記事:認知症はまだ先の話?──“その時”に備える終活のすすめ
認知症に備えてできること
任意後見制度の活用

認知症が進行すると、自分の意思で契約をしたり、財産管理をすることが難しくなります。
そこで注目されているのが、判断能力があるうちに信頼できる人と契約を結んでおく「任意後見制度」です。
将来的に認知症などで判断力が低下した際、この契約に基づき代理人が本人の生活や財産を守ります。
法定後見制度と違い、自分で後見人を選べる点が大きなメリットです。
宇都宮市では、成年後見制度を利用しやすい環境を整えるための機関として、「宇都宮市成年後見支援センター」が令和5年10月に開設されました。
市民後見人制度をご存知ですか?

一定の研修を受けた地域の人が後見人となる「市民後見人」という制度もはじまっています。
「市民後見人普及啓発イベント」にて「栃木県初の市民後見人」殿塚氏とコラボ。終活講座を今井が担当しました。
市民後見人とは、家庭裁判所に選ばれ、認知症や障害などで判断能力が不十分な人の生活や財産を支援する成年後見人の役割を、専門職ではない一般の市民が担う制度です。
専門職の後見人(弁護士や司法書士など)だけでは支援が行き届かないという課題があり、高齢者の増加に伴いより地域に密着した支え手が必要とされ、市民が担い手となる「市民後見制度」が生まれました。
一定の研修を受けた地域の人が後見人となり、身近な立場から本人を見守り支えます。地域に根ざした支援者として、高齢者の安心した暮らしを支える存在です。
遺言書・民事信託の検討
 認知症が進行すると、自筆証書遺言の作成は無効になる可能性も出てきます。
認知症が進行すると、自筆証書遺言の作成は無効になる可能性も出てきます。
そのため、元気なうちから遺言書の準備をしておくことが大切です。
また、資産管理の柔軟な仕組みとして注目されているのが「民事信託」です。
たとえば、親が子に信託財産を託し、自分の生活費として必要な分だけ管理・運用してもらうことが可能です。
将来の財産トラブルや相続争いの予防策としても有効です。
民事信託士紹介 │ 一般社団法人 民事信託推進支援センター(栃木県)
地域の支援と相談窓口を知っておく
認知症に関する相談や支援体制は、地域でも広がりを見せています。
-
認知症地域支援推進員:自治体に配置され、本人や家族の相談窓口になります
-
認知症初期集中支援チーム:医師・看護師・ケアマネジャーなどが早期支援を行います
地域包括ケアシステムの構築に向けた取組 │ 宇都宮市 -
認知症サポーター養成講座:正しい知識を地域に広げる取り組み
認知症パートナー養成講座 │ 宇都宮市
まずはお住まいの地域包括支援センターに相談してみるのがおすすめです。支援につながる第一歩になります。
◆地域包括支援センターとは
高齢者の健康面や生活全般に関する相談を受け付けている、地域に密着した総合相談窓口です。各市区町村に設置されており、高齢者および高齢者を支える人たちが利用できます。
相談できる内容は、日常生活でのちょっとした心配事から、病気、介護、金銭的な問題、虐待など多岐にわたります。
フレイルと脳の健康──動くことが最大の予防
最近では、「フレイル(虚弱)」と認知症の関係も注目されています。
フレイルとは、加齢によって心身の活力が低下した状態。進行すると介護が必要な状態になりやすいですが、早めの対応で改善が見込めることがわかっています。
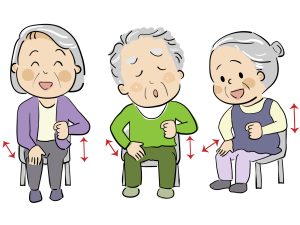 特に効果的なのが運動習慣です。
特に効果的なのが運動習慣です。
-
ウォーキング
-
体操・筋トレ
-
ダンスや有酸素運動
-
手足を使った複合的な運動(コグニサイズ)
脳トレというと計算問題やパズルといったものを連想しがちですが、「脳を鍛えるには、まず体を動かすことが重要」と言われています。考えてみれば、脳も身体の器官ですものね。
さらに、人との交流や地域活動への参加も脳の刺激になり、認知機能の維持に大きな効果があります。
朗報!認知症の発症率は低下傾向に
希望の持てるデータとして、認知症の発症率はここ数年でやや減少傾向にあるという研究報告も出ています。
健康意識の高まりや、生活習慣・栄養への配慮が影響していると考えられています。
つまり、予防と備えによって、未来を変えていくことができる時代なのです。
長寿化の話題はネガティブな内容が多いですが、希望を持てる話題もあります。私も終活講座でよくこの話をしています。
私たちの取り組み──脳トレ講座・コグニサイズ教室・法律講座
終活サポート ワンモアでは、「生きがいづくり」と「予防」に重点を置いた活動を継続しています。
- 遺言/後見人制度/家族信託講座:認知症・おひとりさまに備える法律知識
-
脳トレ講座:ゲームや会話、記憶力を使ったワークで脳を活性化
-
ウォーキング教室:老後も自分の足で歩くための健康ウォーキング
-
コグニサイズ教室:運動と認知課題を組み合わせたプログラム(国立長寿医療研究センター提唱)
地域包括支援センターの協力で、認知症サポーター養成講座も開催しました。
地域での介護予防や認知症対策に、これからも貢献していきます。
「備え」は未来への安心
認知症は、誰にでも起こり得る身近な課題です。
しかし、正しい知識を持ち、制度を活用し、生活習慣を見直すことで、希望を持って未来に備えることができます。
備えることは、ただ不安に向き合うのではなく、自分らしく、よりよく生きるための選択。
その一歩を、今から踏み出してみませんか?
※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)