「介護医療院」とは──医療と介護の“あいだ”を埋める新しい選択肢
「もう病院には置いておけません」と言われたら…

親が長期入院していた病院から突然、「医療的な治療は一段落したので、退院先を探してください」と言われた。けれど、在宅介護は難しいし、特別養護老人ホーム(特養)も空きがない。そんなとき、候補として挙がるのが「介護医療院」です。
でもこの「介護医療院」、名前だけではその中身がよくわからず、混乱する人も多いのが実情です。
制度の背景──「長期入院の終わり」としての介護治療院の登場
介護医療院は、2018年に創設された比較的新しい介護保険施設です。その背景には、「病院に長く入院しすぎてしまう」日本独自の医療慣習への見直しがあります。
高度な治療が不要になった患者が病院にとどまることで、医療費の増大や医療資源の逼迫(ひっぱく)という課題が指摘されていました。こうした中で、介護と医療の両方を提供できる施設として介護医療院が設置されました。
医療から介護へ、施設から在宅へ
日本の高齢化は、世界でも類を見ないスピードで進んでいます。2023年時点で、65歳以上の高齢者は3,622万人。総人口の29.1%を占めています(総務省統計局)。
かつては、高齢者が病気や衰弱で入院すると、そのまま病院で長期療養するのが一般的でした。しかし、医療費の増大や病床不足などの理由から、政府は「医療から介護へ、施設から在宅へ」という流れを強く推し進めるようになりました。
その中で、これまでの「介護療養型医療施設(療養病床)」が廃止され、代わって2018年から設けられたのが「介護医療院」です。
🏥 介護療養型医療施設から「介護医療院」へ
かつての介護療養型医療施設(療養病床)は、医療と介護の中間的な役割を担っていました。
しかし、医療依存度の低い人が長期入院するケースもあり、介護保険の理念と乖離してきたため、2018年度からは「介護医療院」への移行が制度化されました。
介護医療院は長期的な療養と日常生活を支える医療・介護を一体的に提供する新たな施設です。
介護医療院とは?どんな特徴があるの?
 介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です(介護医療院とは?:厚労省)
介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です(介護医療院とは?:厚労省)
介護医療院は、以下のような特徴を持つ施設です。
-
医療と介護の両立:
医師や看護師が常駐し、医療処置や看護、リハビリテーションを提供するとともに、日常生活の世話や機能訓練を行います。
-
長期療養への対応:
要介護度が高い高齢者や、医療ニーズが高い高齢者が、安心して長期療養生活を送れるように設計されています。
-
生活施設としての機能:
プライバシーに配慮した療養室や、食堂、レクリエーション室、機能訓練室などを備え、生活の場としての機能も重視されています。
-
地域との連携:地域住民やボランティアとの交流を積極的に行い、地域に開かれた施設を目指しています。
-
医師・看護師が常駐:
慢性的な病気や日常的な医療ケアが必要な人を対象とする -
介護保険が適用される施設:
病院ではなく「介護施設」扱い -
看取りケアにも対応:
最期まで安心して過ごせる体制
「医療的ケアが必要な人のための特養」といったイメージでしょうか。
特養では対応しきれない中〜重度の医療ニーズがある場合、介護医療院が選択肢になるという説明の方が適切かもしれません。
介護医療院は、医療ケアが必要な高齢者が生活の場として長期に過ごすことを前提に作られた施設です。
病院ほどの医療機能はありませんが、介護施設よりは医療的対応に優れています。
例えば:
-
24時間看護師常駐、医師による定期的な診察
-
褥瘡(床ずれ)や喀痰吸引、経管栄養などの医療的ケアが可能
-
介護スタッフ・リハビリ職・管理栄養士などがチームで支援
-
「看取り」や終末期医療にも対応
病院のような「治す場所」ではなく、生活と療養を両立する「暮らす場所」として設計されています。
数字で見る介護医療院の現状
介護医療院は制度創設からまだ間もないため、整備が進行中です。
-
2023年6月末時点:全国794施設(46,848床)
-
2024年4月時点:全国926施設まで拡大
出典:介護医療院の開設状況について(厚労省資料)
「医療から介護へ」という政策の背景
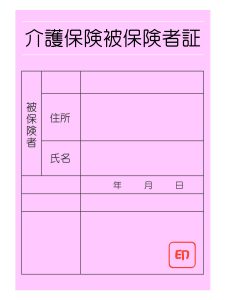 この制度の背景には、「慢性期医療にかかる医療費を抑え、できるだけ介護保険で対応したい」という政策があります。
この制度の背景には、「慢性期医療にかかる医療費を抑え、できるだけ介護保険で対応したい」という政策があります。
従来は、医療保険で長期入院することが一般的でしたが、
-
高額な医療費の負担
-
医療資源の偏在(入院患者数の地域差)
-
医療の場にふさわしくない“生活者”の長期入院
こうした問題を受け、「医療行為があっても、生活を大切にする施設で過ごしてもらおう」という発想に転換されました。
しかし、この政策がすべての現場でうまくいっているとは限りません。
父の終末期に感じた“制度と現実のズレ”
私の父が終末期を迎えたとき、急性期病院からの退院が検討され、介護医療院への転院を熱心に勧められました。しかし父は、輸血やCV(中心静脈)点滴など、かなり高度な医療行為が日常的に必要な状態でした。
相談員の方は「介護医療院でも医療ケアは受けられますよ」と言いましたが、実際には対応できる施設が限られ、CV管理や輸血の継続は困難であることがわかりました。
なぜこのような“ミスマッチ”が起きるのか?
-
病院側の都合(病床確保・在院日数制限)
-
制度の方向性に沿った「転院圧力」
-
現場の情報不足(施設の医療体制の理解不足)
-
患者個々の医療ニーズと制度の想定のギャップ
こういった、制度と現場とのミスマッチがあると言われています。
また、制度上は「看取りも可能」とされていますが、実際の医療水準やスタッフ体制を含めた「対応力」は施設によって大きく異なるようですので、鵜呑みにするのは危険だと思います。
ホスピスを探す際にも同様のことが言えると思います。
介護医療院は「誰のための施設」なのか
介護医療院は、医療依存度が中程度の人や、看取り期にある人にとっての新しい選択肢です。しかし、すべての人に最適とは限りません。
特に、
-
高度な医療行為を日常的に必要とする方
-
状態が急変しやすい方
などは、別の選択肢(医療療養病床や在宅医療体制の充実)も含めて慎重に検討する必要があります。
💬 介護医療院は医療保険の対象外?
これまで手厚い医療保険に加入してきた方にとって、介護医療院は「医療ケアも受けられる施設」と聞くと、一見すると安心な選択肢に思えるかもしれません。しかし実際には、介護保険施設であるため、入所中の費用に対して医療保険からの給付が適用されないことがあります。
「医療型老人ホーム」との誤解から、加入していた医療保険が使えると思い込んでいた…というケースも。医療保険が適用されるのは、原則として病院への入院です。給付条件は保険商品ごとに異なるため、事前に保険会社への確認を強くおすすめします。
また、介護医療院は「介護保険施設」であり、原則として医療行為も含めて介護保険の給付で賄われます。ただし以下のようなケースでは、医療費が自己負担になることがあります。
-
入院が必要になった場合(外部医療機関へ転院した場合は医療保険)
-
介護保険適用外の処置(特殊な処方薬や自己希望の検査)
-
医療と直接関係ない日用品費や室料差額など
この点は医療現場や施設での説明不足があると、本人・家族の誤解や負担感につながるため、制度の周知と情報提供が求められます。
栃木県内の主な介護医療院と相談先
栃木県内にも複数の介護医療院があります。医療対応の範囲や面会ルールなどは施設によって異なるため、事前の相談や見学が不可欠です。
主な介護医療院
-
宇都宮介護医療院(宇都宮市)
TEL:028-661-1165
施設サイト - 介護医療施設だんえん(日光市)
TEL:0288-32-2210
施設サイト -
介護医療院 ふじぬま(栃木市)
施設サイト -
苅部太陽の家(小山市)
施設サイト
相談窓口
-
栃木県 高齢対策課 介護サービス班
県内全域の相談対応窓口PDF一覧はこちら:
相談窓口一覧PDF
選択肢のひとつとして、正しく理解を
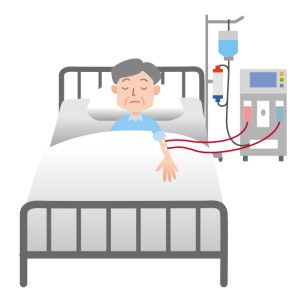 介護医療院は、医療と介護の中間に位置する存在として重要な役割を果たしています。
介護医療院は、医療と介護の中間に位置する存在として重要な役割を果たしています。
しかし、「医療が受けられる」と過信したり、「名前が似ているから特養と同じ」と誤解してしまうと、家族にとっても本人にとっても思わぬ不都合が生じることも。
親や自分の将来を考えるとき、この施設が「どんな人のためにあるのか」「何ができて何ができないのか」を知っておくことが、後悔しない選択につながります。
介護医療院は、制度としては期待されていますが、運用面ではまだ成熟途上の側面もあります。
「医療が必要になったら病院」「介護が必要になったら施設」と単純に分けられないのも現実。
医療と介護の“あいだ”を埋める仕組みを、私たち自身が知り、考えることが、将来への備えになるのではないでしょうか。
📌 関連記事リンク集
※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)
 長寿社会・高齢化2026年1月22日超高齢社会を「体験」して見えてきたこと ― コミュニティコーピングから考える終活支援
長寿社会・高齢化2026年1月22日超高齢社会を「体験」して見えてきたこと ― コミュニティコーピングから考える終活支援 認知症・フレイル対策2026年1月15日高齢者の3人に1人が認知機能低下?いま知っておきたい『認知症保険』
認知症・フレイル対策2026年1月15日高齢者の3人に1人が認知機能低下?いま知っておきたい『認知症保険』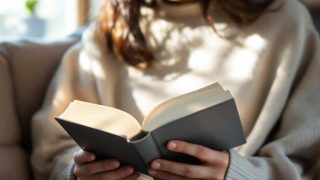 おすすめの終活本2026年1月6日小説から終活を考える ― 人生を見つめるおすすめの本
おすすめの終活本2026年1月6日小説から終活を考える ― 人生を見つめるおすすめの本 相続・遺言2025年12月12日家族に何をのこすのか──遺言から考える「相続の本質」と他人事ではない今日的課題
相続・遺言2025年12月12日家族に何をのこすのか──遺言から考える「相続の本質」と他人事ではない今日的課題


