「まだ死なないけど、このままじゃ生きられない」― ミッドライフクライシス、そして人生の再起動
NHKドラマ『ひとりでしにたい』が描くもの
NHKドラマ『ひとりでしにたい』は、表面上はコメディタッチで描かれていますが、人生の後半戦に突入した人々の“迷い”“焦り”“孤独”といったテーマに真正面から向き合っている点で、非常に意欲的な作品です。
シニアの「終活ドラマ」ではない理由
一般的な“終活”を扱うドラマは、シニア世代が「人生の締めくくり」をどのようにするかに焦点を当てることが多いですが、
『ひとりでしにたい』の主人公・そして彼女を取り巻く人物たちは、まだ「人生の途中」にいます。
キャリア、結婚、介護、老後資金……
まだ「何かを選び直せる」年齢
しかし「もう若くない」ことも自覚している
決断の猶予がない焦りと、残された時間をどう生きるかという葛藤。
これはまさに「ミッドライフクライシス(中年の危機)」を主題にした構造です。
ミッドライフクライシスは、一般的に40代から50代にかけて経験する、人生における心理的な危機のことです。この時期には、仕事や家庭、健康など、さまざまな面で悩みや葛藤を感じやすくなります。「第二の思春期」とも言われることがあります。
コメディ仕立ての意味
甘く味付けされたコメディタッチの演出は、ただ現実をやわらげるためではなく、視聴者が自分ごととしてテーマに入りやすくするための入口になっています。
笑いながらも、「ああ、わかる」と共感させられるセリフや状況の数々は、痛みを含んだ笑いであり、そこにこの作品の深さがあります。
緻密な世相描写
介護の現場のリアル
親の老いと「自分が親の背中を追っている」ことへの気づき
結婚、子ども、キャリアといった人生設計がかつてのモデル通りにいかない現代の現実
そして「老後の孤独」が突然訪れるわけではなく、“中年期の延長線上”にあるものだという事実
これらが、過剰な演出に頼ることなく、淡々と、でもしっかり描かれている点で、極めて現代的なドラマになっています。
 老後問題というよりも、ミッドライフクライシスを描くドラマとして評価すべき作品だと思います。
老後問題というよりも、ミッドライフクライシスを描くドラマとして評価すべき作品だと思います。
そして、それはシニア支援や終活に携わる人たちにとっても非常に重要な視点です。
なぜなら、「終活」は、老いてから始まるものではなく、中年期の葛藤の中にその入口があるからです。
「まだ死なないけど、このままじゃ生きられない」
中年たちの迷いにこそ、真の終活の原点がある──そんなメッセージも、このドラマから受け取れます。
ミッドライフ・クライシスと「人生の再起動」
― 40代・50代から始まる、新しい可能性の物語 ―
人は、年齢を重ねながら進化する
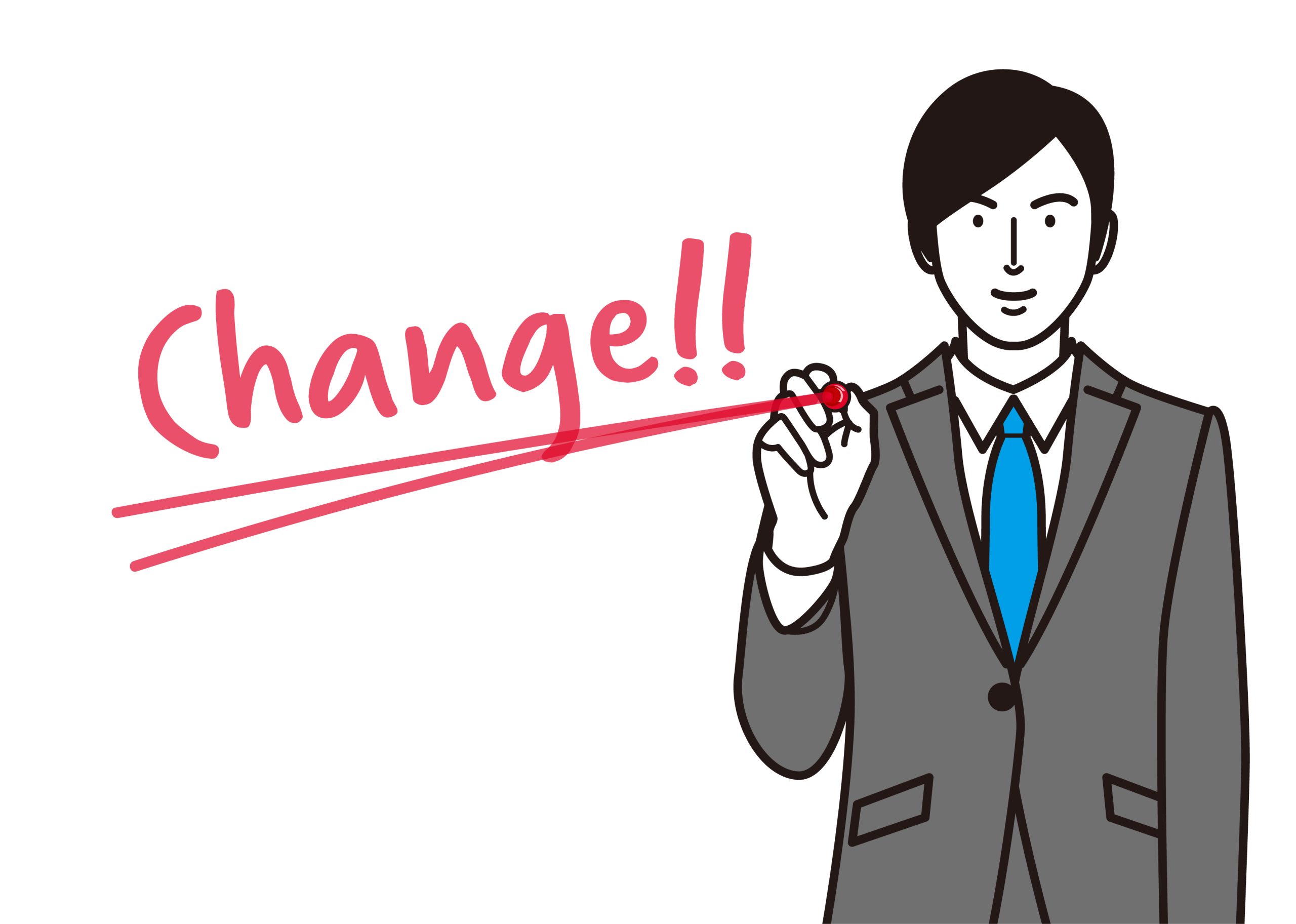 発達心理学では、40代前後はアイデンティティが一度崩壊し、脱皮する時期とされています。
発達心理学では、40代前後はアイデンティティが一度崩壊し、脱皮する時期とされています。
つまり、中年期に「別人のようになる」ことは、決して異常ではなく、ごく自然な心理的プロセス。
この時期、人はふと立ち止まり、
「これからどう生きていくか」
「自分は誰のために、何ができるのか」
といった問いに向き合い始めます。
ここからの生き方次第で、人生の後半はまったく異なるものになる。
それが、ミッドライフ・クライシスの本質なのかもしれません。
ある日ふと訪れる“違和感”
40代になると、外から見れば順調に人生を歩んでいるように見えても、
心のどこかにふと浮かぶ「このままでいいのか?」という思い。
昔ほど夢中になれることがない
仕事にやりがいを感じなくなる
家族や自分自身との関係が変わってきた気がする
なんだか心が空っぽのように感じることがある
それらは、「ミッドライフ・クライシス(中年の危機)」と呼ばれる人生の転機かもしれません。
ですが、これは崩壊ではなく“再構築”の始まりです。
自分とは何者か――再び問われるアイデンティティ
20代や30代でつくり上げた「自分らしさ」や「成功のかたち」が、40代・50代になると揺らぎ始めます。
本当にやりたかったことは何だったのか?
誰の期待を背負って生きてきたのか?
今のままの延長線上に、望む未来はあるのか?
こうした問いは、苦しくもありますが、同時にとても創造的な問いでもあります。
なぜなら、「ここからの人生を、どう生きていきたいか」を自分自身で選び取るチャンスだからです。
衰えではなく、変化としての“老い”
ここで注目したいのが、近年の脳科学研究です。
なんと、人間の脳は80歳になってもなお成長を続けるという結果が報告されています。
若い頃のように瞬発的な記憶力や体力は落ちていく一方で、
論理的思考力、抽象的な判断力、感情のコントロール、人生の意味を読み取る力など――
「成熟の脳力」が発達していくというのです。
つまり、人生の後半には「若さの力」に代わる、「深さと広がりをもった力」が備わってくるということ。
これは、体力や肩書きに依存しない新しい人生の土台を築くチャンスです。
50代は「選び直す」ための貴重な時期
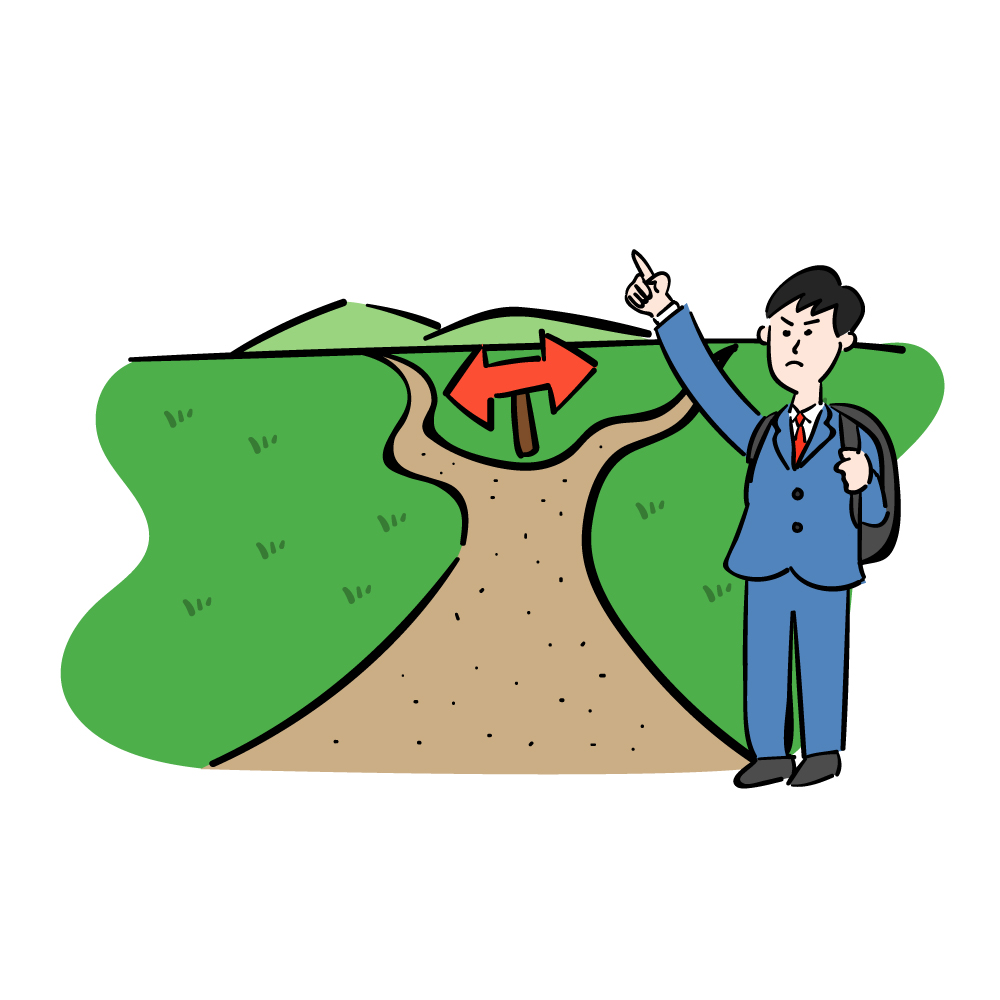 50代は、自分の人生を一度客観視し、軌道修正する大きなチャンスでもあります。
50代は、自分の人生を一度客観視し、軌道修正する大きなチャンスでもあります。
これから何を手放し、何を残すか
どんな人と、どんな場所で過ごしたいか
自分の経験や思いを、どう社会や次世代に活かしていくか
「人生の後半だからこそできること」が、確かに存在します。
それは若さの代わりに得た「深さ」「つながり」「本質への感度」といった、成熟の力があってこそ。
本当の可能性は、いつでも“今の外側”にある
「もう若くないから」「変わるには遅すぎる」と思いがちですが、人の可能性は、年齢ではなく“意識と行動”で決まるのかもしれません。
脳が80歳まで成長し続けるように、人生もまた、いつからでも“再起動”できるのです。
クライシスの先に、新しい生き方がある
ミッドライフ・クライシスは「終わり」ではなく、「始まり」のサインです。
いま感じている揺らぎや迷いは、自分が変化しようとしている証拠。
“変われる今だからこそできること”に目を向けて、「本当に大切にしたいもの」を選び直し、これからの人生を、自分の手で再設計していきませんか?
ポジティブとは、現実を直視する力でもある
ここでお伝えしておきたいのは、前向きに生きようという提言は、決して能天気なポジティブシンキングではないということです。
むしろそれは、
自分の中にある不安や迷い
喪失や後悔といった過去の痛み
これから訪れるかもしれない別れや衰え
――そうしたネガティブな現実にしっかりと目を向けることから始まります。
逃げるのではなく、見つめ、受け止める。
そのリアリズムこそが、本当の意味での前向きさを支えてくれるのです。
これは、終活にも通じます。
死という“避けられない現実”を正面から見つめるからこそ、
いまこの瞬間をどう生きるかという問いがより深く、かけがえのないものとして、私たちの人生に響いてくるのです。
いくつになっても、人生は“更新”できる
 年齢を重ねることは、「終わっていくこと」ではなく、変化のなかで「新しい問いを生きていくこと」なのかもしれません。
年齢を重ねることは、「終わっていくこと」ではなく、変化のなかで「新しい問いを生きていくこと」なのかもしれません。
人生の後半にも、まだ見ぬ可能性と出会うチャンスが待っています。
ネガティブを抱えながらでも、自分らしく歩き続けること。
その姿は、やがて誰かの希望にもなっていきます。
迷いや不安は、「変わりたい」という心のサイン。
どうかそれを否定せず、大切にしてください。
そして、あなた自身の「これから」を信じて、今から、もう一度、人生を動かしはじめましょう。
※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰 兼 栃木支部長。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催します
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)
 コラム2025年7月17日認知症はまだ先の話?──“その時”に備える終活のすすめ
コラム2025年7月17日認知症はまだ先の話?──“その時”に備える終活のすすめ コラム2025年7月9日「まだ死なないけど、このままじゃ生きられない」― ミッドライフクライシス、そして人生の再起動
コラム2025年7月9日「まだ死なないけど、このままじゃ生きられない」― ミッドライフクライシス、そして人生の再起動 コラム2025年7月4日自分らしい最期をどう迎える?──“葬儀”の備えと選択肢
コラム2025年7月4日自分らしい最期をどう迎える?──“葬儀”の備えと選択肢 コラム2025年6月27日「人生の棚卸し」で、心も暮らしも軽やかに。『生前整理』という新しい習慣
コラム2025年6月27日「人生の棚卸し」で、心も暮らしも軽やかに。『生前整理』という新しい習慣
