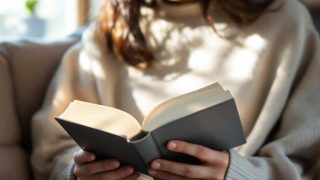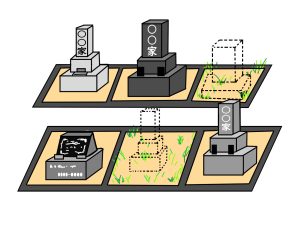「自分らしい死」を選ぶために知っておきたい、終末期医療の現実と選択肢
自然な死に方は本当に可能なのか?
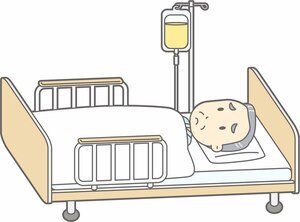 「できれば自然に死にたい」という願いは、多くの人が抱いているものです。終活の現場でも、アンケートでも、そうした声は少なくありません。
「できれば自然に死にたい」という願いは、多くの人が抱いているものです。終活の現場でも、アンケートでも、そうした声は少なくありません。
ですが、現代の日本社会において、その「自然死」は本当に実現可能なのでしょうか?
医学の進歩や栄養状態の改善により、かつてなら命を落としていた病気でも長く生きられるようになりました。その一方で、多くの人が病気を抱えながら生き、やがて病気をきっかけに人生の終わりを迎えるという現実があります。
厚生労働省の統計では、日本人の死因の大半は「病死」。がん、心疾患、脳血管疾患、肺炎などが上位を占め、いわゆる「老衰」は全体のわずか数%しかありません。
現代に生きる私たちは病気と共に生き、最期も何らかの疾患をきっかけに迎えるケースが大半というのが現実なのです。
「自然死」のイメージは人それぞれ
「自然に死にたい」と一言で言っても、その内容は人によって大きく異なります。そもそも、「自然死」の定義自体があいまいで、人によってイメージが異なるのも問題です。
-
医療的な延命措置をせず、静かに息を引き取ること
-
痛みがなく、穏やかに死ぬこと
-
医療や介護に依存せず、できるだけ自立したまま死ぬこと
どれも自然な死に思えますが、どれも一筋縄ではいきません。そもそも老化自体が病気と地続きのプロセスであり、「何もせずに自然に死ぬ」という状態は、極めてまれなのです。
このように、「自然死」という曖昧な理想と、現実の医療・介護のギャップこそが、終末期に向き合う上での本質的な課題といえるでしょう。
緩和ケアとは「よりよく生きる」ための医療
 そこで注目されるのが、緩和ケアです。
そこで注目されるのが、緩和ケアです。
緩和ケアとは、治療の難しい病を抱えた人が、残された時間をできるだけ苦痛なく、自分らしく過ごすための医療や支援のことです。
延命や治癒を第一の目的とせず、QOL(Quality of Life:生活の質)を高めることを重視します。痛みのコントロールだけでなく、不安や孤独といった心のケア、家族への支援も含まれます。
誤解されがちですが、緩和ケアは「死を早めるもの」ではありません。
むしろ、生きている間を大切にする医療です。本人の意志を尊重し、尊厳ある生と死を支える役割を担っています。
特に終末期には、治療よりも「どう穏やかにその人らしく最期を迎えるか」が問われます。そのためには苦痛を抑え、家族との時間や自分自身の想いに向き合える環境が必要です。
ホスピスという選択肢
緩和ケアとともに語られるのがホスピスです。ホスピスは、緩和ケアを専門とする施設や病棟で、がんや難病など、治療が難しい状態の患者さんを対象としています。
ただし、ホスピスにはいくつかの種類があり、理解しておきたい違いがあります。
✅ 病院とホスピスの違い
-
病院:病気を治す・延命することが目的
-
ホスピス:苦痛を和らげ、穏やかに最期を迎えることが目的
✅ ホスピスの種類
-
病院内ホスピス:一般病院の中に設けられた緩和ケア病棟
-
独立型ホスピス:地域に根差した専門施設。より家庭的な雰囲気を大切にする傾向
✅ 医療対応のホスピスも存在する
医師・看護師が常駐し、医療行為を行いながら緩和ケアを提供するホスピスも多く存在します。治療を完全に終える前でも、早期から緩和ケアを受けられるケースもあります。
✅ 数が少なく、費用の壁も
ホスピスの数は病院に比べて圧倒的に少なく、病床数が足りていないのが実情です。また、ホスピスでの費用が医療保険の対象外となる場合もあり、金銭面でのハードルも存在します。
訪問看護という選択肢
「病院やホスピスではなく、自宅で最期を迎えたい」と考える人にとって、訪問看護は非常に大きな支えになります。
訪問看護は、看護師や医療スタッフが自宅を訪問し、療養生活を支えるサービスです。点滴や痛みのコントロール、褥瘡(じょくそう)のケア、ターミナルケア(終末期看護)まで幅広く対応します。
訪問看護の特徴:
-
自宅にいながら専門的な医療ケアが受けられる
-
かかりつけ医と連携して24時間体制をとっている事業所もある
-
家族にとっても心強いサポートとなる
-
医療保険・介護保険が適用されるため、経済的負担も比較的軽い
しかし現実には、訪問看護を担う人材の不足や地域差が課題となっています。特に地方では訪問看護ステーション自体が少なかったり、夜間や休日の対応が難しかったりすることもあります。また、利用者側が「医療は病院でするもの」という先入観を持っていることも、在宅ケアが広がらない一因とされています。
それでも、「住み慣れた場所で、できるだけ穏やかに過ごしたい」という願いに応える手段として、訪問看護は今後ますます重要になるでしょう。
このように、ホスピスや訪問看護といった多様な最期の選択肢を知り、現実に即した形で自分や家族の意志を確認しておくことが、これからの終活には欠かせません。
尊厳死と安楽死──その違いと日本の課題
「自然死」を考える上で、避けて通れないのが尊厳死と安楽死です。
-
尊厳死:延命措置を望まず、自然な経過で死を迎える選択
-
安楽死:苦痛を和らげるために、積極的に死を早める医療行為
尊厳死は、すでに日本でも容認されつつあり、事前に本人の意志(リビングウィル)を示しておくことで、延命治療を控える選択が可能です。
一方、安楽死は法律上も社会的にもまだ非常に慎重な扱いが求められます。
あくまで個人的な意見ですが、私自身は日本社会の忖度文化や同調圧力を考えると、安楽死の導入には慎重であるべきだと考えています。本来、自分自身の意志で選ばれるべき行為が、周囲の期待や空気によって押しつけられる危険性が拭いきれないからです。
終活の本質は「現実との対話」にある
私たちは「理想的な最期」を語るとき、つい「自然に死にたい」と口にしてしまいます。しかし、その理想を叶えるには、現実の医療・ケア・制度としっかり向き合う必要があります。
-
どこで死にたいのか
-
どんなケアを受けたいのか
-
苦痛をどう取り除くか
-
延命を望むかどうか
-
家族とどう話し合っておくか
これらは、元気なうちに考えておかなければならない大切な問いです。
「自然な死に方」を望むことは間違いではありません。しかし、その実現のために必要なのは、現実を知り、選択肢を整理し、意志を表明することなのです。
リビングウィル──「自分の意志」をあらかじめ示す手段
「もしものとき、自分がどんな医療を望むのか」。それを前もって文書にしておくものがリビングウィルです。日本では法的拘束力はありませんが、本人の意志として医療現場で尊重されることが増えてきました。
たとえば…
-
延命治療を希望しない
-
意識がなくなった場合の人工呼吸器の使用は拒否する
-
苦痛緩和を最優先にしてほしい
といった希望を、事前に記しておくことができます。
ただし、リビングウィルはあくまで「本人の考えを書いたもの」であり、状況次第で解釈が分かれることもあります。そこで重要になるのが、家族や医療者との対話です。
家族会議とACP──話し合うことが最も重要な備え
 近年、日本でも注目されているのがACP(アドバンス・ケア・プランニング)です。いわゆる「人生会議」とも呼ばれ、将来の医療やケアについて、本人と家族、医療・介護の関係者が事前に話し合うプロセスを指します。
近年、日本でも注目されているのがACP(アドバンス・ケア・プランニング)です。いわゆる「人生会議」とも呼ばれ、将来の医療やケアについて、本人と家族、医療・介護の関係者が事前に話し合うプロセスを指します。
ACPのポイントは以下の通りです:
-
一度きりの話し合いではなく、繰り返し更新していくプロセス
-
本人の価値観や人生観を大切にする
-
家族が迷わないための手がかりになる
-
医療者と共有しておくことで、緊急時の判断がしやすくなる
「何を選ぶか」よりも、「どう話し合っておくか」が、後悔のない選択に繋がるのです。
「人生の終わり」に、どう備えるか
誰にでも訪れる「人生の終わり」に、どう備えるか。
それは「どう生きたいか」と向き合うことでもあります。
終活は、死に方ではなく、生き方を見つめ直す営みです。
自分らしい最期を迎えるために、今できることから始めてみませんか?
※本記事は、一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)