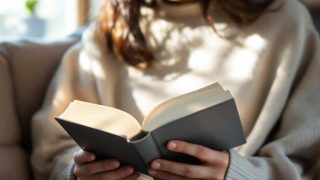「老後破産」を防ぐために、今できることーー貯蓄では乗り切れない時代に必要な6つの備え
“貯めていれば安心”はもう古い?
「年金でなんとかなるだろう」
「退職金と貯金があれば足りるはず」
そんな考えが、もはや通用しなくなってきている現実があります。近年、ニュースや特集でもたびたび取り上げられるようになった「老後破産」。
これは特別な人の話ではなく、誰の身にも起こり得るリスクとなりつつあります。
老後破産とは?
 「老後破産」とは、定年退職後の年金生活の中で、日々の生活費や医療・介護費用が賄えず、経済的に破綻してしまう状態を指します。
「老後破産」とは、定年退職後の年金生活の中で、日々の生活費や医療・介護費用が賄えず、経済的に破綻してしまう状態を指します。
破産申請をするかどうかに関わらず、実質的に生活が困窮している状態を広く指す言葉として使われています。
高齢期に潜む“想定外の支出”と物価高
老後資金の計画において、実は見落とされやすいのが以下のような予期しにくい出費です。
- 医療や介護の自己負担費用の増加
- 子や孫の援助による資金流出
- 配偶者の死去による収入減
- 住まいのリフォームや修繕費用
- 物価の高騰による日常的な支出の増加
特にここ数年はエネルギー・食料品など生活必需品の著しい値上がりが続いており、家計を圧迫しています。
さらに、国際関係の緊張による経済不安定(円安・株価の乱高下・物資の輸入コスト上昇など)も、長期的には年金運用や貯蓄の価値を揺るがす可能性があります。
老後破産の主な原因
老後破産にはさまざまな要因があり、それらが単独で起こるというよりも、複数の原因が複雑に絡み合って生活を圧迫していくケースが多く見られます。
例えば、「年金だけでは足りない」という経済的な問題に、「住宅ローンが残っている」などの固定費の負担が加わり、さらに「病気や介護」といった突発的な支出が重なる――というように、一つひとつは対処可能でも、組み合わさることで深刻化するのが特徴です。
また、高齢者特有の身体的・精神的な変化や、社会的な孤立、制度の情報格差なども、経済的困窮を助長する要因となります。
こうした複合的なリスクを「老後破産」という言葉に集約しているため、原因を知るだけでなく、自分自身の暮らしのなかでどのリスクが重なり得るかを想定し、早めに対策を講じていくことが重要です。
以下に挙げるのは、老後破産を引き起こしやすい代表的な原因です。
- 年金だけでは生活が成り立たない(特に自営業者や無年金者)
公的年金の支給額は現役時代の収入や保険料納付期間に応じて決まります。特に自営業者や国民年金のみの受給者は、年金額が月6万円前後と少なく、生活費を賄うには不十分な場合が多いです。無年金の高齢者も一定数おり、生活保護に頼らざるを得ないケースもあります。 - 退職金や貯蓄の取り崩しペースの誤算
老後資金を一括で確保していても、「どのくらいのペースで使えばよいか」という見通しを誤ると、予想よりも早く資金が尽きてしまいます。特に、初期のリフォームや旅行などで大きな支出が続くと、後年に不足に陥る可能性が高くなります。 - 住宅ローンが退職後も残っている
退職までに住宅ローンを完済できなかった場合、年金収入でローン返済を続けることになり、生活費を圧迫します。リバースモーゲージや売却も選択肢としてありますが、条件やリスクを十分に理解しておく必要があります。 - 高齢者世帯の孤立と、相談先のなさ
高齢になると人とのつながりが減り、困りごとを誰にも相談できずに抱え込んでしまうことがあります。結果として、金銭的に不利な契約を結んだり、生活支援制度の活用ができず、経済的困窮に陥ることも少なくありません。 - 認知症や体力低下による金銭管理の困難
認知症の進行や身体機能の衰えにより、銀行手続きや支払いの管理が難しくなり、未納や詐欺被害につながることがあります。また、悪意のある他人による財産侵害もリスクの一つです。後見制度などの準備が重要です。 - 長寿化により、想定より長い老後を送ることになる
日本では90代まで生きる人が珍しくなくなっており、「老後が30年以上続く」という現実が現役世代にものしかかっています。長寿化は喜ばしいことですが、同時に、資産の長期運用と支出コントロールが必須になります。
「長生きリスク」と呼ばれるように、老後が30年以上に及ぶ時代では、貯蓄をいかに長く持たせるかが鍵となります。
今後の展望:制度改革と社会的課題
現在、日本政府も以下のような対策に乗り出しています:
- 公的年金の改革(受給開始年齢の選択制拡大など)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISAの普及
- 高齢者の就労支援・定年延長政策
- 高齢者向け生活支援や家計相談窓口の充実
しかし、制度の整備と個人の対策にはタイムラグがあり、今すぐ生活を立て直したい高齢者にとっては“今この瞬間の支援”が必要です。
解決策・備えのための行動
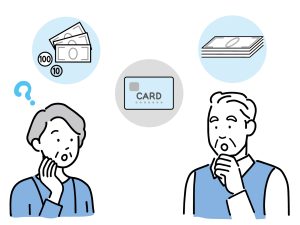 1. 家計の「見える化」
1. 家計の「見える化」
収支のバランスを定期的にチェックし、**固定費の見直し(保険・通信費・サブスクなど)**を行いましょう。
2. 「ライフプラン表」で老後を数値化
年齢ごとの支出予測と収入見通しを立て、人生100年時代に合わせた資金計画を。
金融機関や終活支援の専門家のサポートも有効です。
3. 地域資源の活用
市区町村の行政相談窓口や、社会福祉協議会、包括支援センター、消費生活センターなど、無料で相談できる機関が多くあります。
また、地域で開催される終活支援イベントやライフプラン講座なども、情報収集や仲間づくりの良い機会です。
4. 誰に相談するかにも注意を
老後資金の悩みを軽く知人に打ち明けた結果、悪徳業者を紹介されたり、詐欺商法に巻き込まれたという事例も少なくありません。
「絶対儲かる投資」「損をしない仕組み」など甘い言葉には要注意。金融・福祉の専門家や公的機関での相談を優先しましょう。
5. 住まいの見直し
高額な住宅維持費や固定資産税を抑えるため、住み替えやダウンサイジングも選択肢の一つです。
6. 収入を完全に絶たない工夫
週1〜2回の短時間勤務や、趣味を活かした内職など、緩やかな就労継続が、経済的にも精神的にも支えになります。
「備えあれば老後破産なし」
老後破産は“特別な人だけの問題”ではありません。現役時代に安定収入を得ていた人でも、見通しの甘さや想定外の支出によって一気に生活が苦しくなることは十分にあり得ます。
だからこそ、定年前の早い段階からの備え、そして退職後も定期的な生活設計の見直しが必要です。
お金の悩みは「正しい場所で」話すこと
お金の話は、誰にでもしにくいものです。ですが、孤立したままでは不安は解消しません。
- お住まいの自治体にある「高齢者相談窓口」「生活支援センター」
- 終活支援団体や地域包括支援センター
- 金融機関や社会福祉士による無料相談
など、安全で信頼できる窓口を活用することが、トラブルを防ぐ第一歩です。
“話せる場所”があれば、老後の不安は少しずつ和らぎます。正しい情報を得て正しい行動を、それが「安心して年を重ねる」ための最も現実的な方法です。
※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)