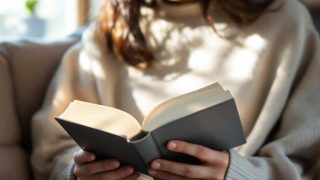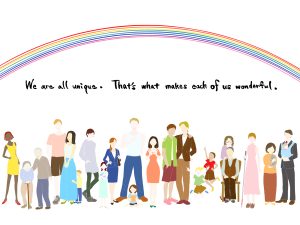【保存版】個人事業主・一人親方の「終活」ガイド 〜属人化リスク、廃業準備、承継問題まで〜
なぜ今「個人事業主の終活」が必要なのか
 個人事業主・一人親方にとって、業務はすべて「自分が動けること」が前提になっています。しかし、突然の事故や大病、認知症の発症といった健康上のリスクにより、ある日突然、業務が継続できなくなる可能性も否定できません。実際に「契約が途中で止まった」「家族が内容を把握できず混乱した」「事後処理が長期化した」などの声も聞かれます。
個人事業主・一人親方にとって、業務はすべて「自分が動けること」が前提になっています。しかし、突然の事故や大病、認知症の発症といった健康上のリスクにより、ある日突然、業務が継続できなくなる可能性も否定できません。実際に「契約が途中で止まった」「家族が内容を把握できず混乱した」「事後処理が長期化した」などの声も聞かれます。
このような非常時への備えも含め、事業と人生を整理する“終活”の視点がますます重要になっています。
日本には約1450万人のフリーランス・個人事業主(※1)が存在し、就業者全体の2割以上を占めるとされています。
また、中小企業庁のデータによると、個人事業主の多くが60代以上で、事業承継の準備ができていないケースも少なくありません(※2)。
「後継者がいない」「事業が個人に依存している」「何をどう整理すればよいかわからない」
そんな声が現場では多く聞かれます。
社会全体が高齢化し、働き方が多様化する今、個人事業主こそ“ライフシフト”と“終活”を結びつけて考えるべき時代になっています。
医師・経済学者のリンダ・グラットン氏らが提唱した概念で、「人生100年時代」において、教育→仕事→引退という従来の3ステージ型人生から、複数のキャリアや役割を持ちながら柔軟に生きる生き方への転換を指します。終活も「死に支度」ではなく、人生後半のライフシフト=生き方の再設計ととらえることが求められています。
個人事業主ならではのリスクと課題
会社員と違い、個人事業主は「経営者」と「労働者」を一人で担っています。
日々の仕事に追われる中で、もしもの備えや将来の計画は後回しにされがちです。
しかし、体調不良や高齢化、社会の変化により、ある日突然“続けられなくなる”可能性も否定できません。
個人事業主の終活では、以下のような課題が浮上します。
1. 属人化による事業継続困難
-
仕事の進め方、取引先との関係、顧客管理などがすべて“自分の頭の中”に。
-
引き継ぎが困難で、廃業後に顧客が困るケースも。
2. 資産管理の線引きが曖昧
-
生活費と事業費が混在。
-
死亡時に相続人が「何が事業用で何が個人用か分からない」。
3. 社会保障の空白
-
国民年金だけでは老後資金が不十分。
-
傷病・介護・死亡時のセーフティネットが薄い。
4. 廃業・承継の手続きが複雑
-
税務署や自治体、保険関係の届け出が多岐にわたる。
-
準確定申告や契約解除手続きなど、家族に大きな負担が。
5. 情報の散在・デジタル遺品問題
-
顧客情報、会計データ、SNS、クラウドなどが未整理。
-
パスワード不明でアクセスできないリスク。
これらの課題は、ひとりで抱え込まず、早めに整理・対策を始めることが大切です。
自治体の相談窓口や専門家のサポートも活用しながら、無理のない終活を進めていきましょう。
今から備えられる5つのアクション
✅ 1. 事業資産の見える化
-
取引先リスト、契約書、帳簿、機材・在庫の棚卸し。
-
ファイルの整理とクラウド活用、パスワード管理。
✅ 2. 制度の活用(任意加入)
-
小規模企業共済(事業主の退職金制度)
- 労災保険特別加入(けが・病気時の補償 ※3)
-
国民年金基金・付加年金(老後資金の上乗せ ※4)
- 就業不能保険や医療保険(万一に備える)
✅ 3. 廃業・承継シナリオの準備
-
廃業届・青色申告の停止届の手順確認
-
承継候補の検討、引継書の作成
-
顧客への案内文テンプレートの用意
✅ 4. 家族・関係者と情報共有
-
「どこに何があるか」を家族に伝える
-
必要に応じてエンディングノートの活用
✅ 5. セーフティネットと公的支援の相談
-
商工会議所、地域の中小企業支援センター
-
日本政策金融公庫の事業承継融資
-
厚労省・自治体による個人事業者向け相談窓口
必要に応じて、税理士・社労士・地域包括支援センターなどの専門機関にも相談しながら、自分らしい「仕事と人生の整理」を進めていきましょう。
公的な相談・支援窓口一覧(主なもの)
終活や廃業、事業承継、ライフプラン設計に関する不安は、一人で抱え込まず、公的な支援機関を活用するのが安心です。
無料相談が可能なところも多く、状況に応じた具体的なアドバイスを受けられます。
| 窓口 | 内容 | URL・連絡先 |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 廃業・承継・資金繰り相談 | https://www.jfc.go.jp |
| 中小企業基盤整備機構(ミラサポplus) | 承継・再起業支援 | https://mirasapo-plus.go.jp |
| 労働基準監督署(特別加入相談) | 一人親方の労災特別加入 | 各地域の労基署へ |
| 商工会・商工会議所 | 経営相談・記帳指導など | 地域の窓口へ |
| 地方自治体の産業振興課 | 創業・廃業の届出、助成金など | 役所HPで確認 |
📌 相談時の注意とアドバイス
・なるべく事前に状況を整理してから相談(メモ・資料があるとスムーズ)
・匿名や仮名での相談が可能な機関もあります(初回相談など)
・「一つの窓口で全て解決」は難しいので、必要に応じて複数機関を活用しましょう
「いざという時に困らない」ための業務・資産の棚卸し
 とくに個人事業主の場合、仕事の多くが自分一人に依存しているため、家族や関係者が「何から手をつければいいのか分からない」状況になりがちです。
とくに個人事業主の場合、仕事の多くが自分一人に依存しているため、家族や関係者が「何から手をつければいいのか分からない」状況になりがちです。
その結果、廃業の手続きや顧客対応が滞り、信頼・資産・時間のすべてを失うリスクさえあります。
そこで重要になるのが、「棚卸し(見える化)」です。
このチェックリストは、自分の事業や契約関係、資産、使用ツール、公的制度の加入状況などを整理・記録しておくための実用的な第一歩です。
やってみると意外と忘れていた契約や、家族が知らないままだった重要な情報にも気づけるはずです。
個人事業主向けに、以下のようなチェックリストやワークが有効です。
📌 <保存版>廃業・承継チェックリスト
個人事業は、仕事も資産もすべてが“自分次第”。でも、事故・病気・高齢化などで突然仕事が止まってしまったら?
家族も取引先も混乱しないよう、「何がどこにあり、誰が関わっているか」をリストアップしておくことが、終活の第一歩になります。
※ 重要度・必要性の観点から優先順位をつけて整理していくのが理想です。
■ 業務関係
-
主要な取引先リスト(名称・連絡先・契約内容)
-
サブ契約・下請けなどの外注先一覧
-
使用中の請求・会計ソフト、クラウドツール、管理者情報
-
SNSアカウント(X、Instagram、YouTube等)と運用ルール
-
自社HP、ドメイン、サーバー契約、ログイン情報
■ 資産・契約
-
事業用口座・クレジットカード
-
事業で使っている不動産・設備・車両等
-
リース・レンタル契約一覧(PC・複合機等)
-
保険契約(医療・損保・所得補償など)
■ 届出・公的手続き
-
税務署への開業・廃業届、青色申告の届出
-
労災特別加入、国民年金基金、付加年金
-
市区町村への事業関係の届出(業種による)
-
廃業後の失業手当や各種社会保険の手続き
-
家族や相続人に知らせるべき内容の整理
📌 <保存版>ライフシフトに備える10の問い
「終活」と聞くと、どうしても「老後」や「死への準備」というイメージが強いかもしれません。
でも実際には、今の自分と未来の自分をつなぐ「生き方の見直し」でもあります。
この10の問いは、自分のキャリアや価値観を振り返り、これからの生き方と事業の方向性を再設計するためのものです。
→ 自分の仕事の意味、今後やりたいこと、家族との共有、今後の生き方を内省。
-
自分の仕事は、誰のどんな役に立っているか?
-
この仕事で、何にやりがいや誇りを感じているか?
-
事業が突然止まったら、困る人・困ることは?
-
代わりがきく作業と、自分にしかできない作業は?
-
今の仕事を10年後も続けたいと思うか?
-
事業を誰かに任せるとしたら、何を残したい?
-
仕事以外に、やってみたいこと・学びたいことは?
-
健康や家族の問題で働けなくなったらどうする?
-
人生100年時代を、どんな風に生きたい?
-
自分が不在でも安心できる仕組み、ある?
すでに終活に取り組んでいる方ならお気づきかもしれませんが、「個人事業版エンディングノート」ですね。
これらを活用して業務や仕事のビジョンと、プライベートや人生観を結びつけて棚卸しをすることで、「人生と仕事を同時に整理する」視点が持てます。
紙に書き出して見える化することで、これまで曖昧だったものが「共有できる形」に変わります。
家族や信頼できる仲間とともに、この作業を少しずつ始めてみましょう。
人生の幕引きと事業の幕引き
 個人事業主にとっての「終活」は、単なる資産整理ではなく、
個人事業主にとっての「終活」は、単なる資産整理ではなく、
「どう生きて、どう手渡し、どう引くか」という人生哲学にも関わることです。
事業をたたむ勇気
後進にバトンを渡す知恵
これまで積み重ねてきた価値を、未来へつなぐという決意と覚悟
個人だからこそできる、しなやかで柔軟なライフシフトのかたちを、今から描いていきましょう。
参考・統計データ
-
※1 総務省「就業構造基本調査(2022年)」
-
※2 中小企業庁「中小企業白書2023」
-
※3 厚労省「労災保険特別加入制度の概要」
※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX
-
終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。
また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。
こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。
終活カウンセラー1級
エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)
ITパスポート
フォトマスターEX
- 近況 -
・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました
・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました
終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。
-----------------------------------------------------------------------------------
・終活相続ナビに取材掲載されました
・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)
・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)